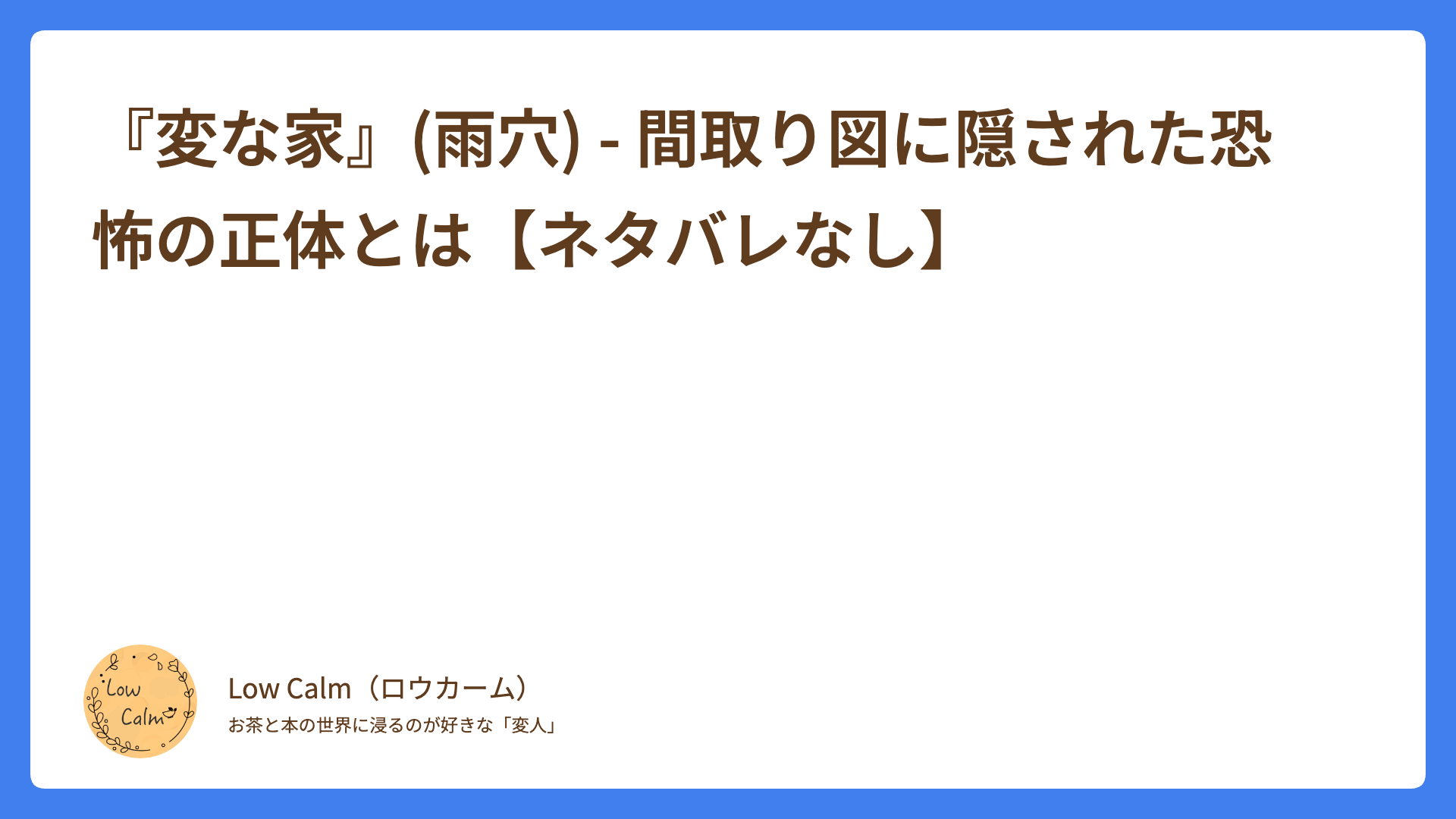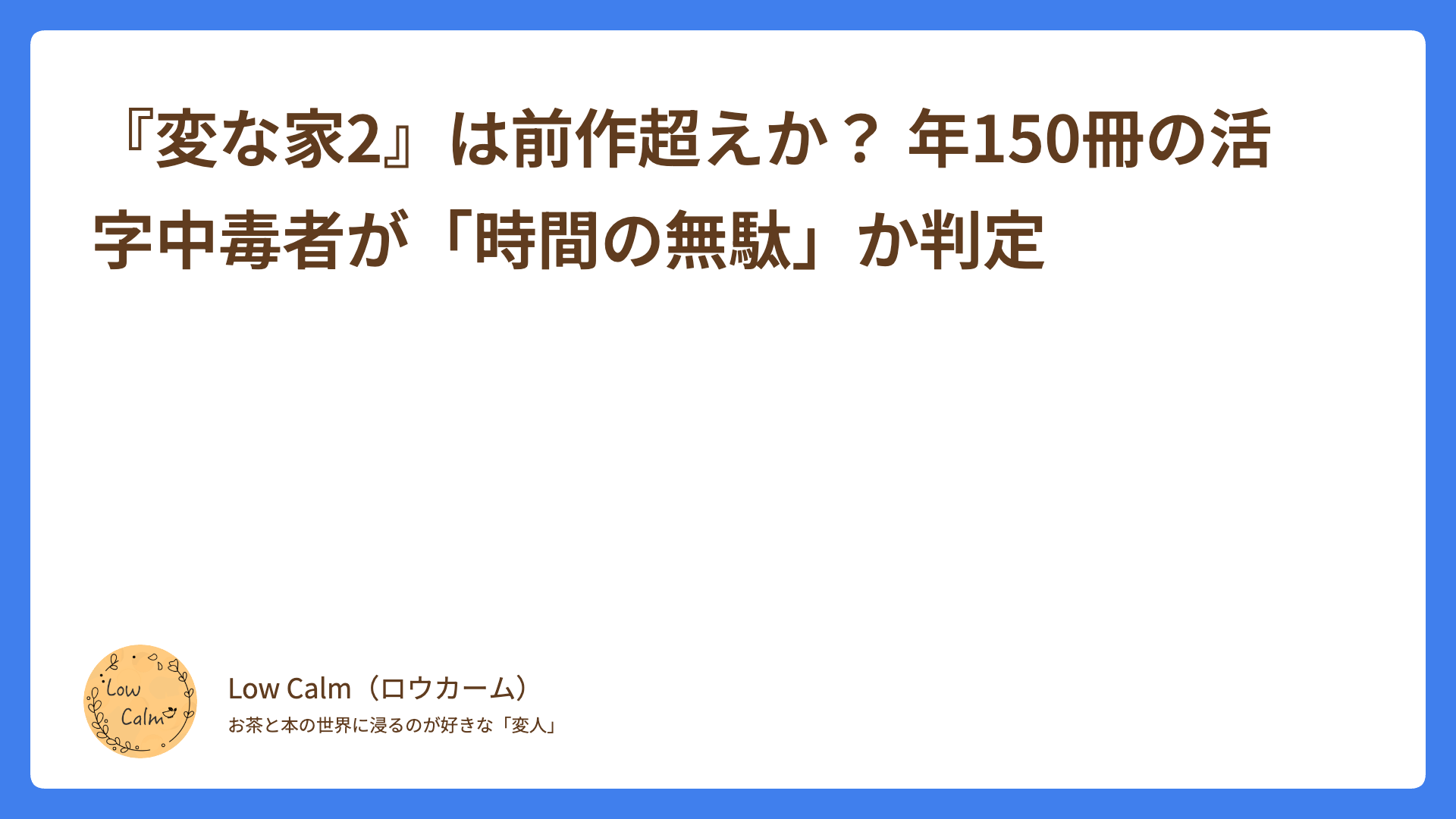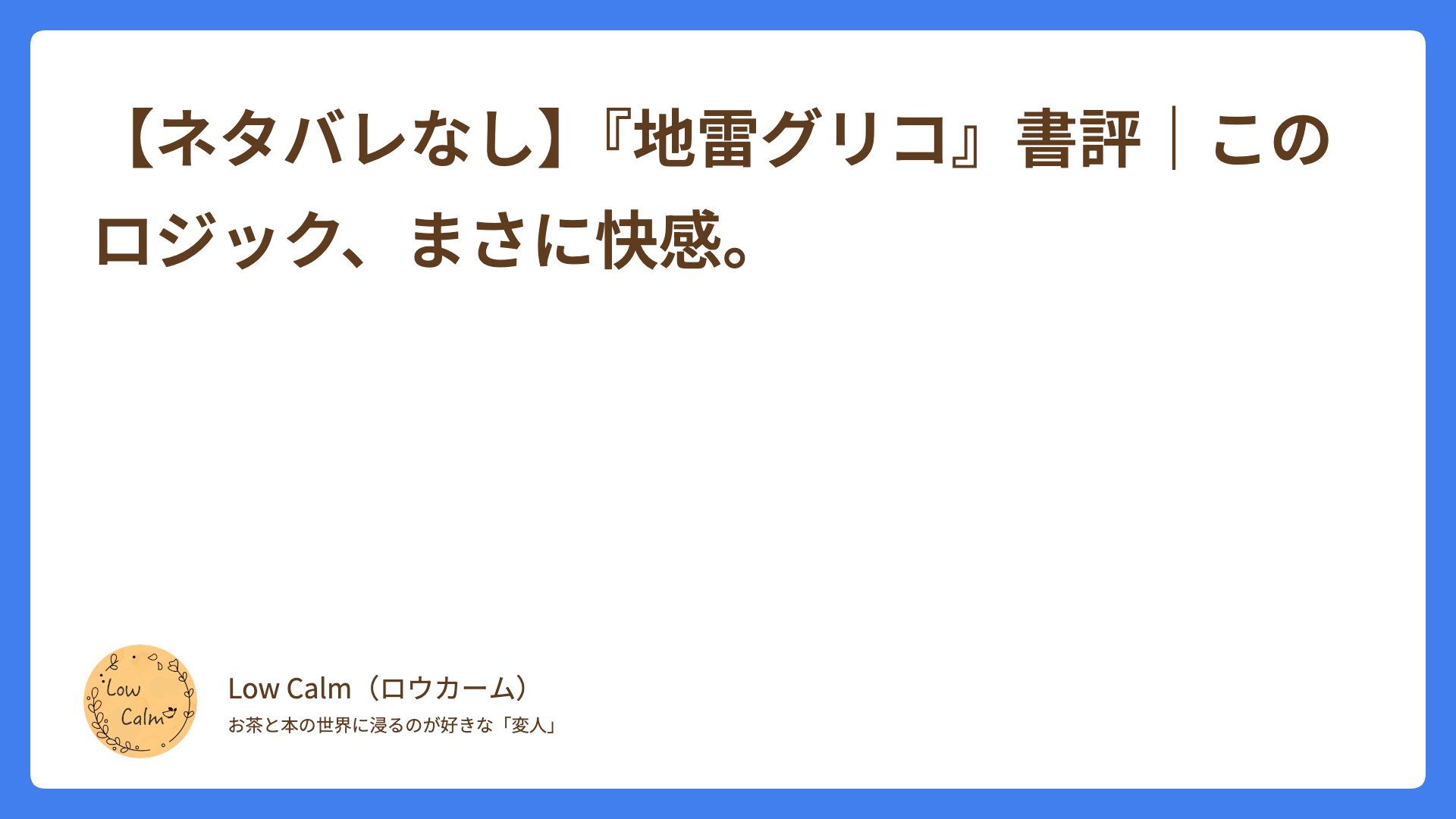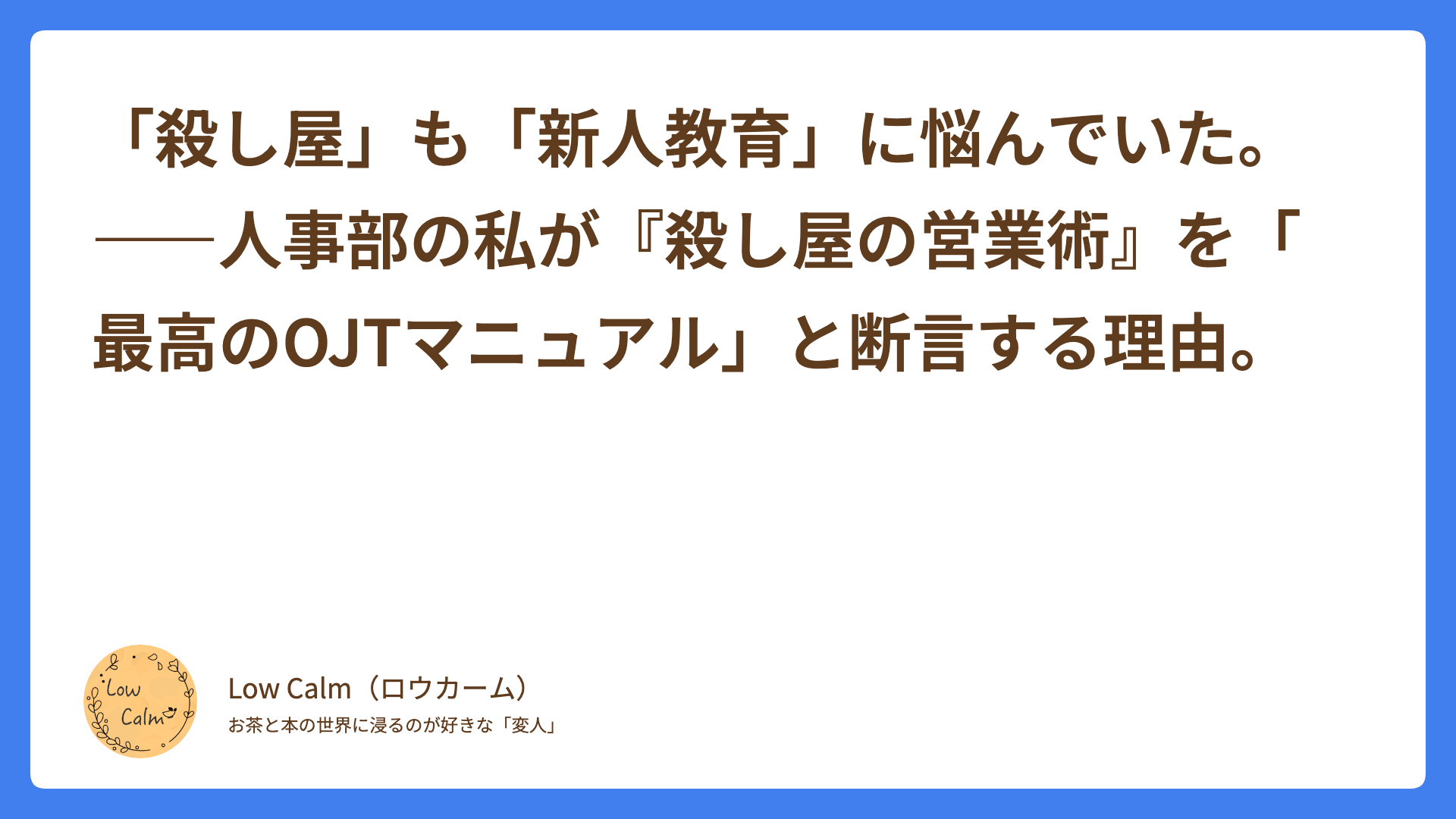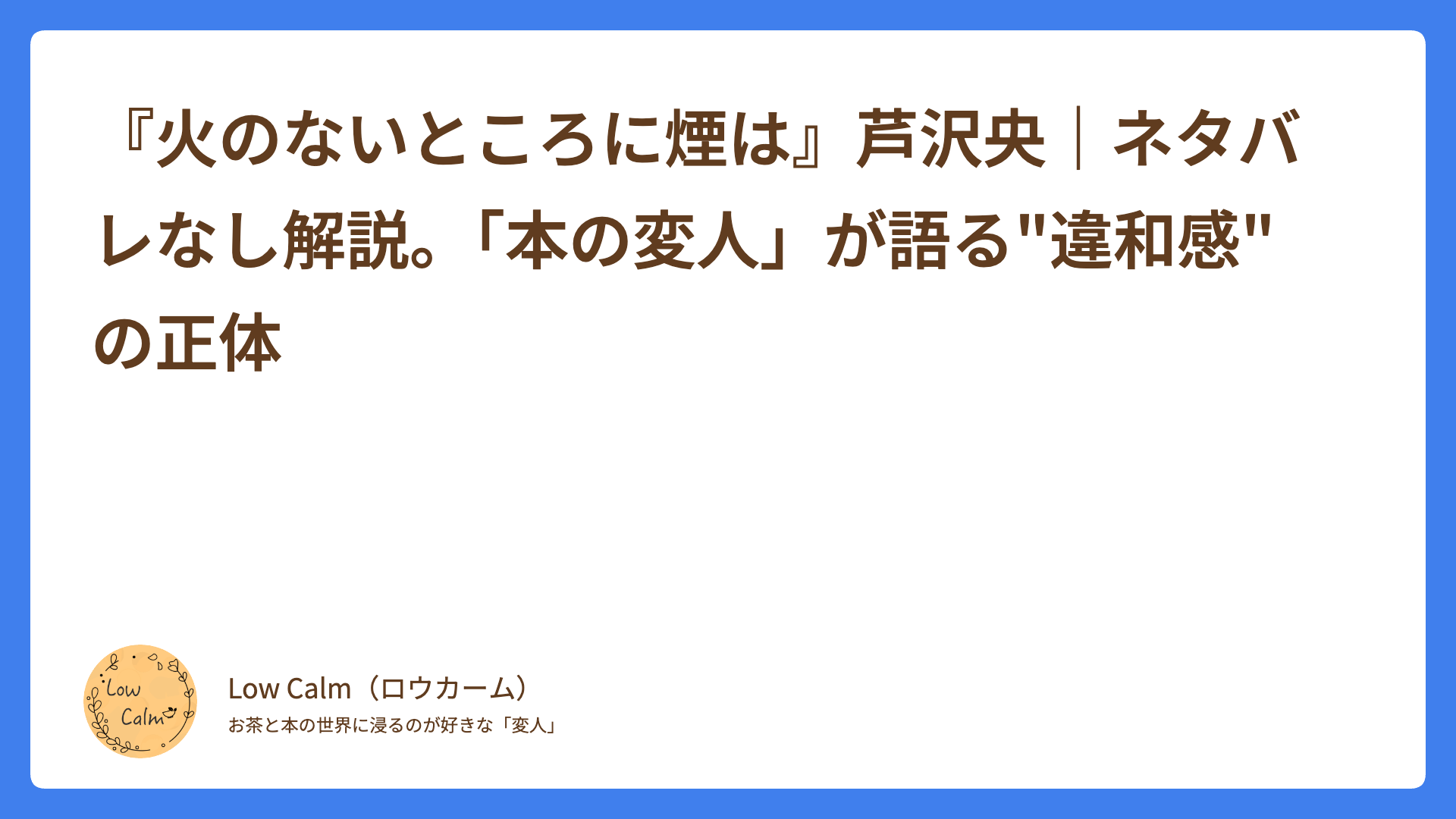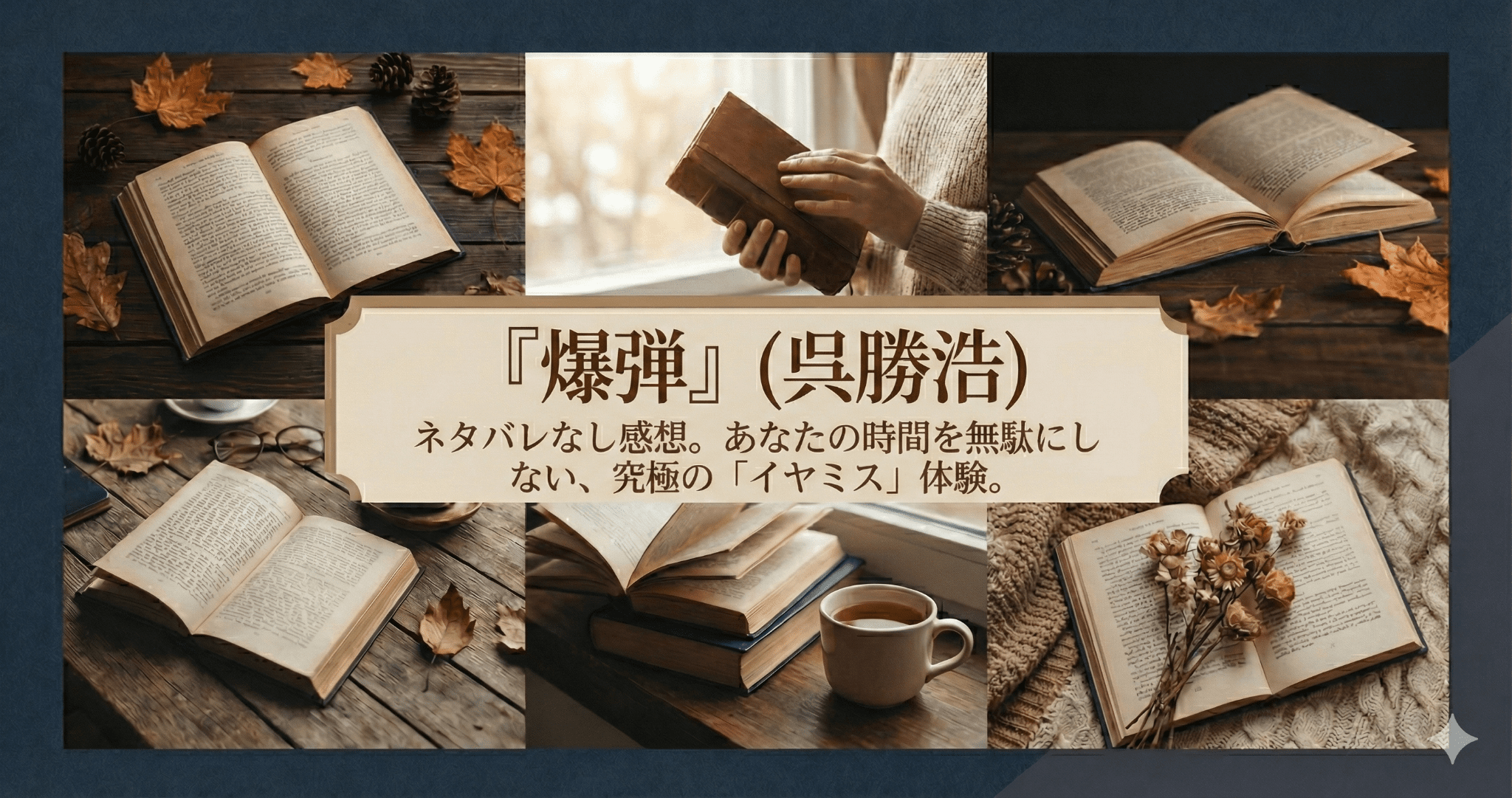「それ、あなたの”職分”ですか?」――仕事に悩む全会社員に、人事部の私が『職分』を叩きつけたい理由。
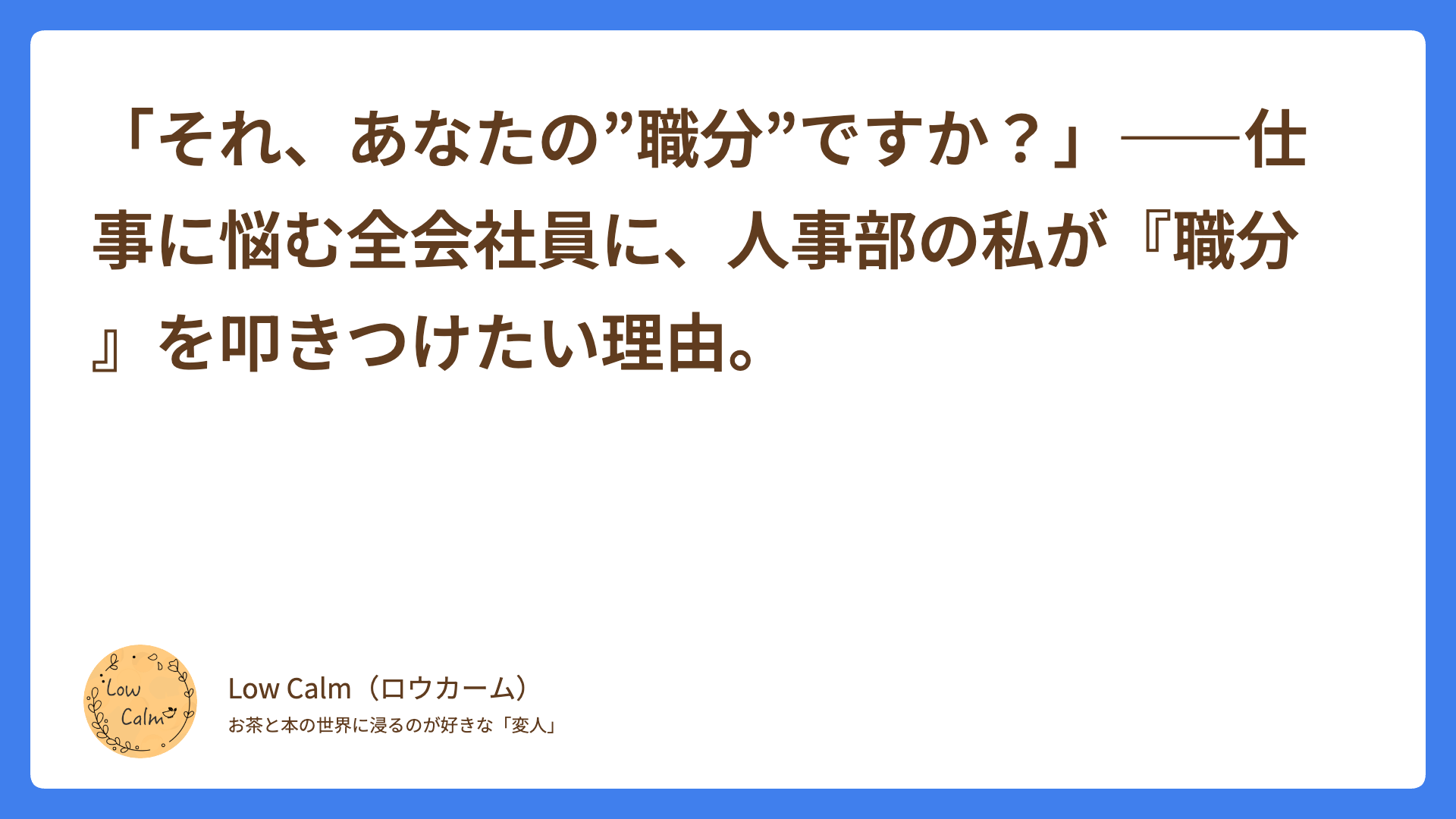
「時間の無駄」。 私、Low calmが読書において最も憎む言葉です。美味しいお茶を淹れる時間、その本を選ぶ時間、そして読む時間。その全てが「失敗」に終わるほど虚しいことはありません。
結論から申し上げます。今野敏氏の『職分』は、あなたが「会社の理不尽」や「組織の縦割り」に息苦しさを感じているならば、その時間を投資する価値のある「最高の組織論テキスト」です。
しかし、もしあなたが派手な銃撃戦や、血湧き肉躍るアクション、あるいは私が愛する「イヤミス(後味の悪いミステリ)」のような強烈な刺激を求めているなら、その時間は確実に無駄になります。今すぐこのページを閉じ、別の本を探すことを強く推奨します。
この記事では、年間150冊の活字中毒者であり、本業で人事労務管理に携わる私(ミステリ愛好家)が、なぜこの「地味な」警察小説を「失敗しない一冊」として確信したのかを、徹底的に解剖します。
この記事でわかること
- 『職分』が単なる警察小説ではない、「組織論」としての真価
- 人事部(私)が心を抉られた、「働くこと」に関する痛烈な描写ベスト3
- あなたがこの本を読むべきか、読まないべきかの最終判断
このブログのモットーは「あなたの時間を大切にすること」。最初だけ読んでも結論はわかります。ですが、最後まで読めば、あなたは明日から「仕事」と「職分」という言葉を、明確に使い分けることができるようになるはずです。
グッときたところベスト3
本書は、千葉県警の刑事・堂木功一朗(どうき こういちろう)を主人公とする警察小説です。「事件」そのものよりも、事件を取り巻く「組織」の闇と光に焦点が当てられています。私が心を掴まれた「プロフェッショナリズムの核心」を、第一位から紹介します。
第一位:主人公・堂木が貫く「職分」の定義
これこそ、私が本業(人事)で日々、全従業員に問い続けたいことです。 「あなたは『作業』をしていますか? それとも『職分』を果たしていますか?」と。
多くの人間は、波風を立てないよう、言われたことだけをこなす「仕事」に逃げ込みます。しかし、主人公の堂木は違います。彼は「刑事」という職分を果たすためなら、警察内部の不文律、キャリアとノンキャリアの壁、他部署との縄張り争いといった「組織の理不尽」に、真正面から立ち向かいます。
彼はヒーローではありません。ただ、自分の「職分」に異常なまでに誠実なだけです。 この「職分」というたった二文字の言葉の重みを、これほどまでに痛烈に突きつけてくる小説を、私は他に知りません。
第二位:吐き気がするほどリアルな「組織のセクショナリズム」
私は活字中毒者であると同時に、ミステリ中毒者でもあります。しかし、本作の「ミステリ(謎)」要素は、事件そのものよりも、この「警察組織という名の伏魔殿」にあります。
なぜ、彼らは協力しないのか。 なぜ、彼らは情報を隠すのか。 なぜ、彼らは「お客様(=県民)」のためではなく、「組織」のために動くのか。
これは、警察小説の形を借りた、現代の「大企業病」のカルテです。 人事部として、私は毎日「部署間の対立」や「無意味な縄張り争い」の仲裁をしています。だからこそ、本書で描かれるセクショナリズムの「くだらなさ」と「根深さ」には、共感と怒りで吐き気すら覚えました。
このリアルすぎる組織の描写こそが、今野敏作品の真骨頂です。時間を無駄にしないどころか、自分の職場環境を客観視する「鏡」として機能しました。
第三位:「解決」ではなく「落としどころ」を探る現実
私は普段、人間の悪意がむき出しになる「イヤミス」を好んで読みます。そこでは「白黒ハッキリつく結末」や「救いのない真実」が描かれます。
正直に告白します。 読む前、私は今野敏氏の警察小説を「予定調和の公務員賛歌」だろうと侮っていました。それは私の時間を無駄にするだろう、と。
しかし、それは甚だしい誤解でした。 『職分』で描かれるのは、そんな生易しいものではありません。 正義を振りかざすだけでは、組織は崩壊する。かといって、不正義を許せば「職分」は果たせない。 このギリギリのバランス感覚の中で、堂木は「正解」ではなく「最適解(=落としどころ)」を探し続けます。
このヒリヒリするような現実主義こそ、管理職や人事担当者が直面する「調整業務」そのものです。 派手なドンパチは一切ありません。しかし、会議室で交わされる言葉の裏側にある「大人の戦い」の緊張感は、下手なアクション小説を遥かに凌駕します。
どんな人におすすめなのか
この本があなたの時間を豊かにするか、それとも無駄にするか。明確に線引きします。
おすすめな人
- 組織の「理不尽」や「縦割り」に悩む、全ての中間管理職 主人公・堂木の「職分」を貫く姿勢は、明日から組織と戦うための「武器」になります。これはあなたのための本です。
- 人事・労務・総務など、組織の「調整役」を担うバックオフィス部門の人 「セクショナリズム」や「落としどころ」の生々しい描写は、あなたの日常業務そのものです。共感と学びしかありません。
- 派手なアクションより、「会議室の緊張感」を楽しむのが好きな人 『半沢直樹』や『七つの会議』のような、言葉とロジックで戦う組織ドラマが好きな人には、最高の読書体験を約束します。
おすすめしない人
- ミステリに「派手なアクション」や「ドンパチ」を求める人 一切ありません。本書の戦場は「会議室」と「電話」です。あなたの時間を確実に無駄にします。
- 複雑な組織図や、登場人物の「役職」を覚えるのが苦手な人 本書の面白さの半分は、「〇〇課の課長」と「〇〇部の部長」の力関係を理解することにあります。これが苦手な人には苦痛です。
- 勧善懲悪。悪い奴がスカッと成敗される「水戸黄門」的ストーリーが好きな人 本書の結末は「最適解」であり、必ずしも「100%の正義」ではありません。現実的な落としどころにモヤモヤする方には向きません。
著者のプロフィール、本の詳細
著者のプロフィール
今野 敏(こんの びん) 1955年、北海道生まれ。上智大学文学部在学中の1978年に『怪物が街にやってくる』で問題小説新人賞を受賞しデビュー。 卒業後はレコード会社に勤務しながら執筆。2006年、『隠蔽捜査』で第27回吉川英治文学新人賞を受賞。2008年、『果断 隠蔽捜査2』で第21回山本周五郎賞、第61回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を受賞。 『ST 警視庁科学特捜班』『ハンチョウ』『隠蔽捜査』など、映像化作品を多数持つ、警察小説・組織小説の第一人者。
本の詳細
- 書籍名: 職分 堂木功一朗
- 著者: 今野 敏
- 出版社: 新潮文庫
- 発売日: 2017年10月28日
- ページ数: 352ページ
まとめ:あなたの時間を投資すべきか
『職分』は、あなたの時間を投資する価値がある一冊でしょうか。
私は、本作の核心をこう読み解きました。
この物語は、「正義」と「悪」の戦いではありません。 「自らの職分を全うしようとする者」と「組織の論理に安住する者」の戦いです。
それは、派手なアクション(私が期待し、そして裏切られた点・第三位)ではなく、リアルすぎる組織のセクショナリズム(第二位)との地味な戦いです。 そして、その戦いを支えるのが、「作業」ではなく「役割」を果たすという、主人公の強烈な職業意識(第一位)なのです。
読む前の私は、人事部の人間として「組織論」には飽き飽きしており、読書にまで仕事の延長を持ち込みたくない、と思っていました。 読後、私は「組織の中で『職分』を果たすこと」の格好良さと尊さを、フィクションの力で再確認させられました。
これは、私の「イヤミス好き」という嗜好とは真逆の読後感でした。 しかし、私の「人事労務」という本業には、これ以上ないほど深く突き刺さりました。 これは「時間の無駄」では断じてありません。むしろ、働くことへの解像度を上げる、最高の「自己投資」です。
あなたに問います。 あなたは明日、会社で「仕事」をしますか? それとも、「職分」を果たしますか?
その答えが曖昧なら、今すぐこの本を読むべきです。