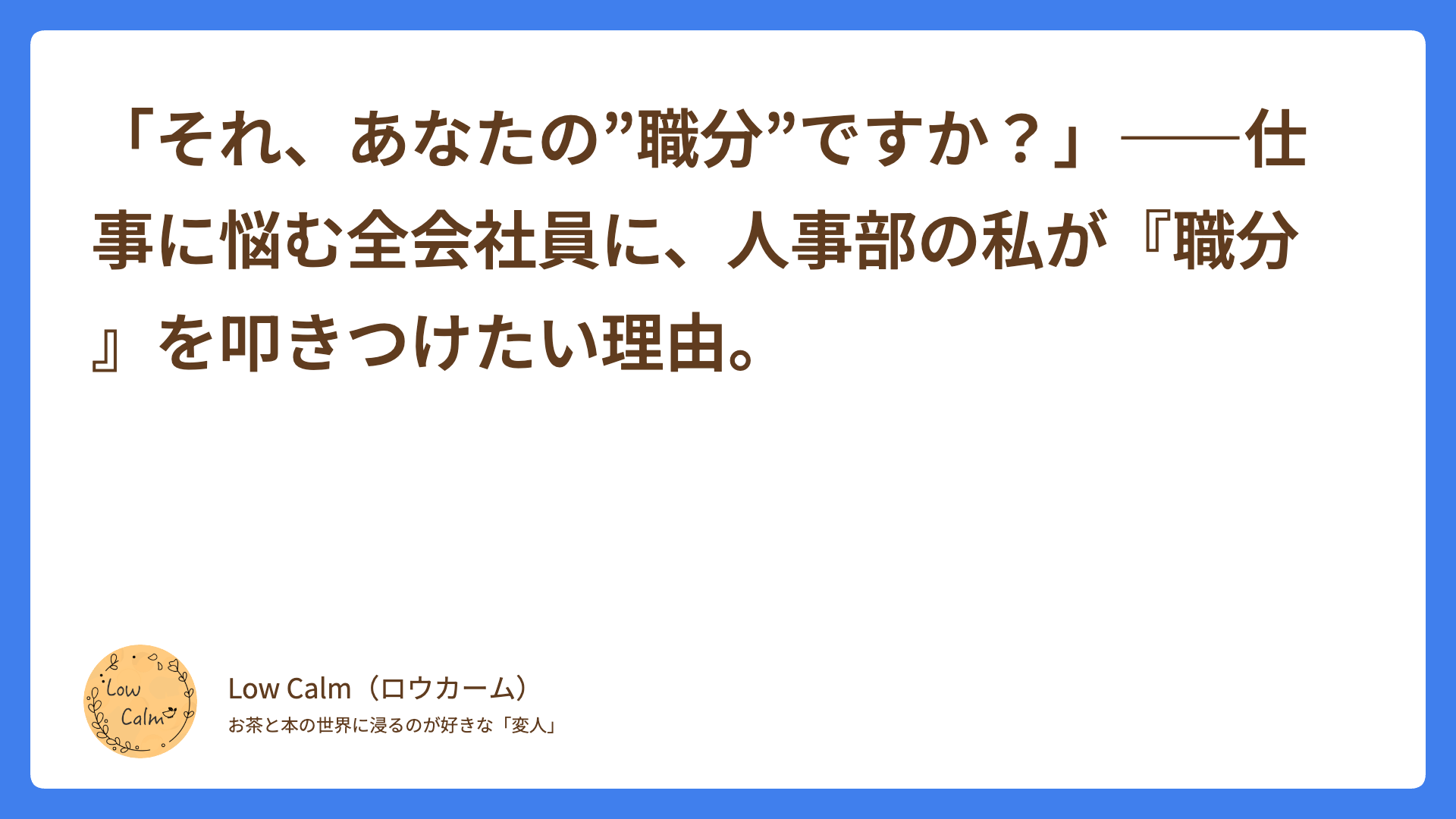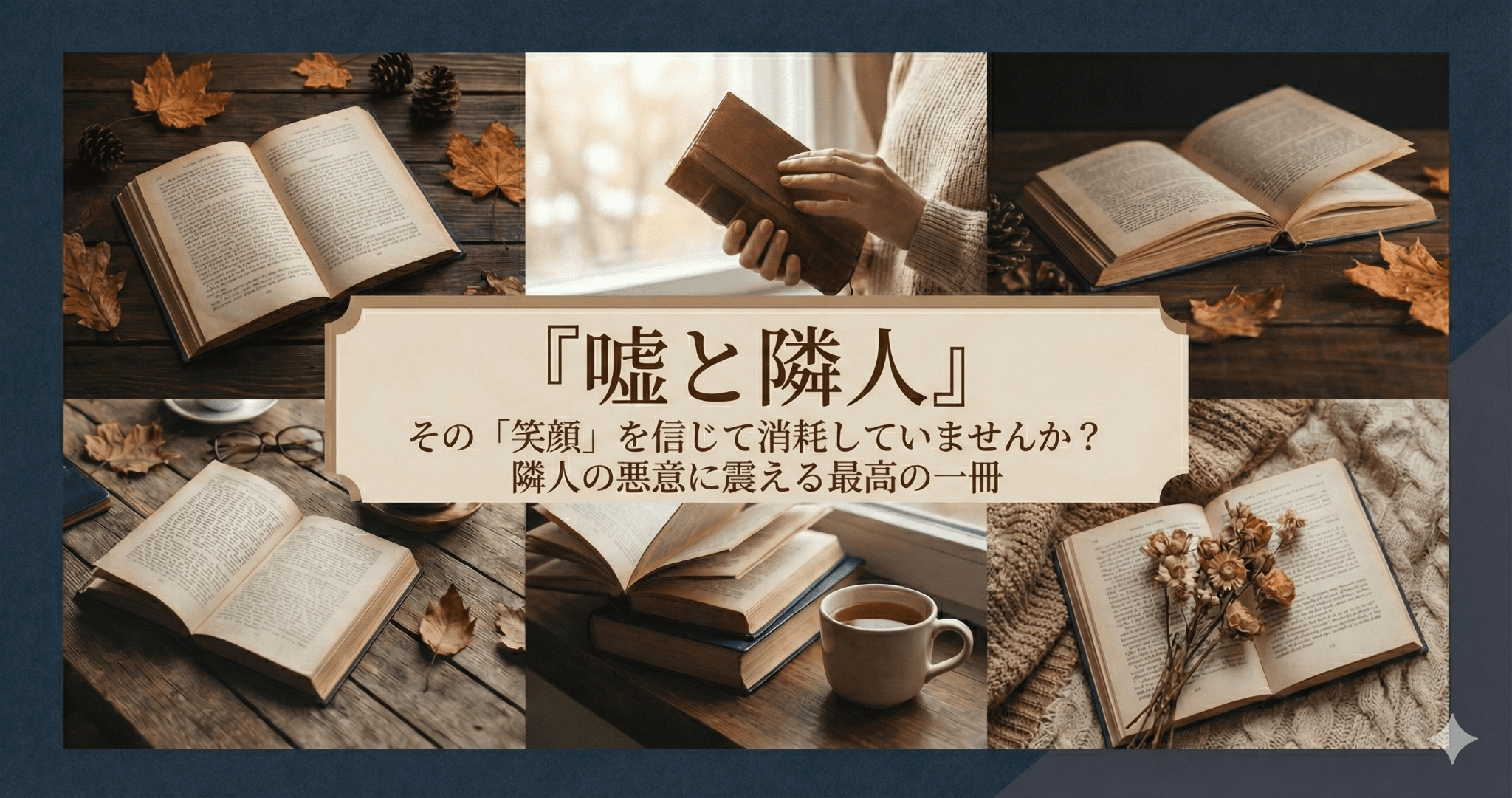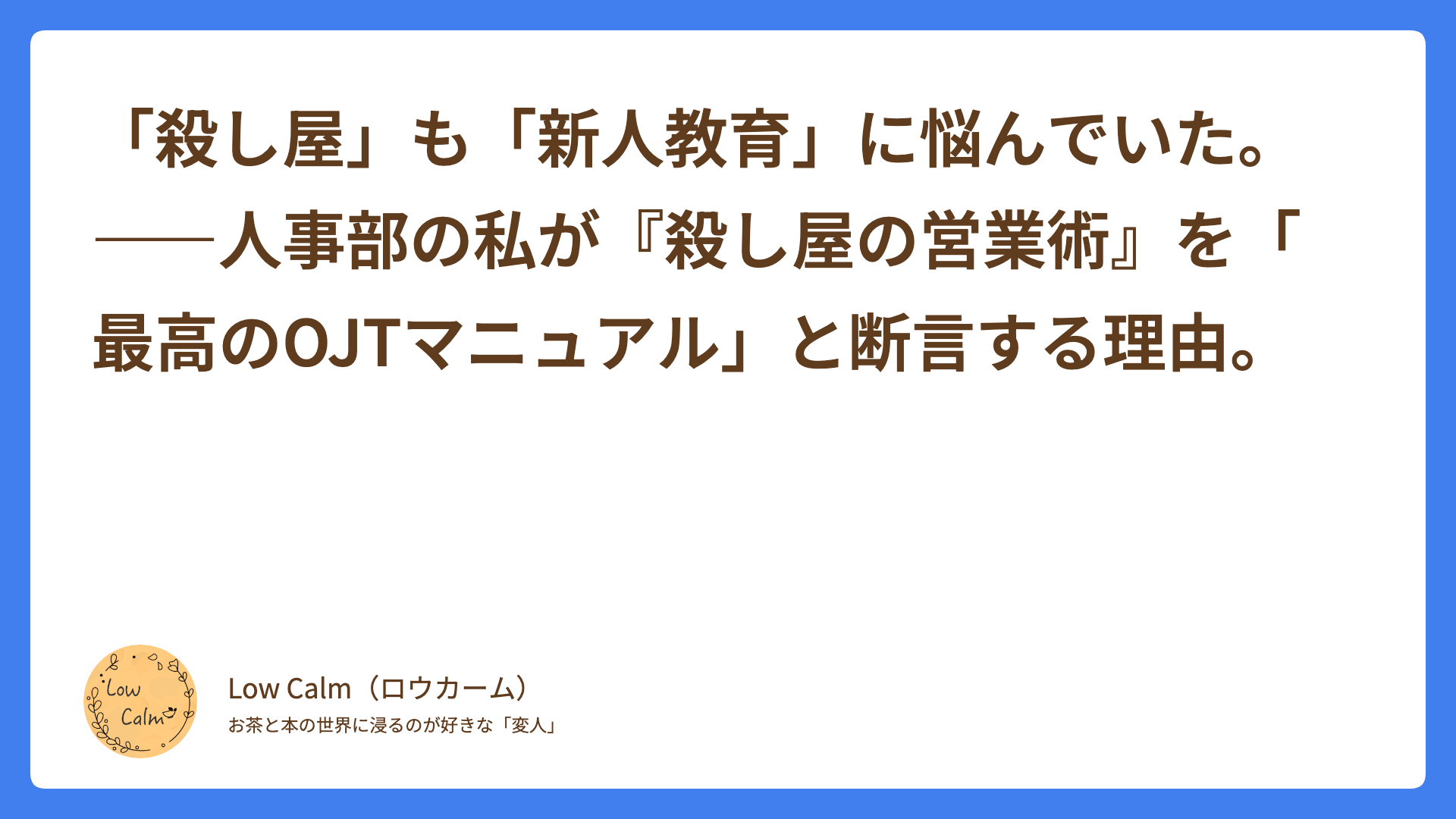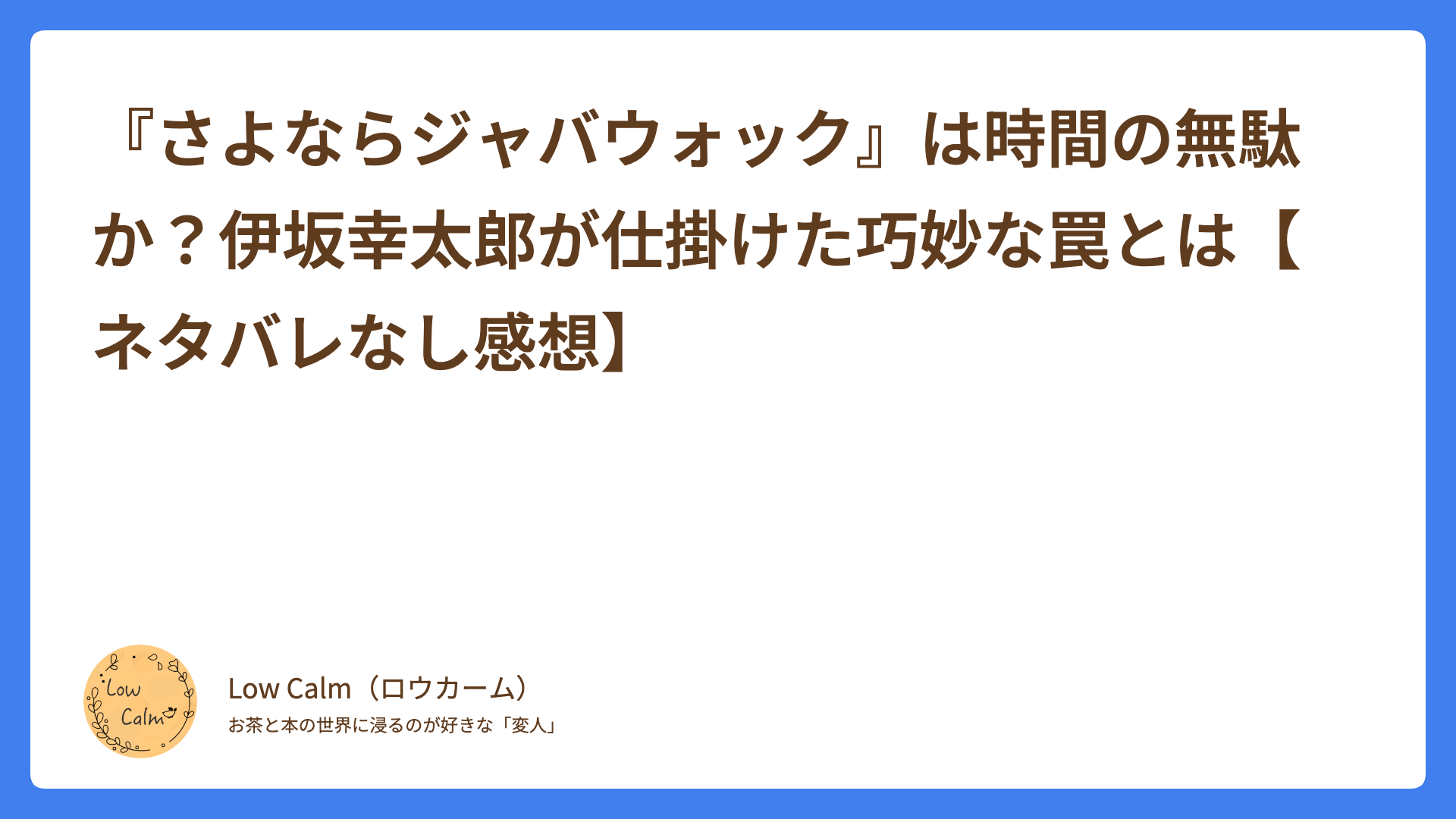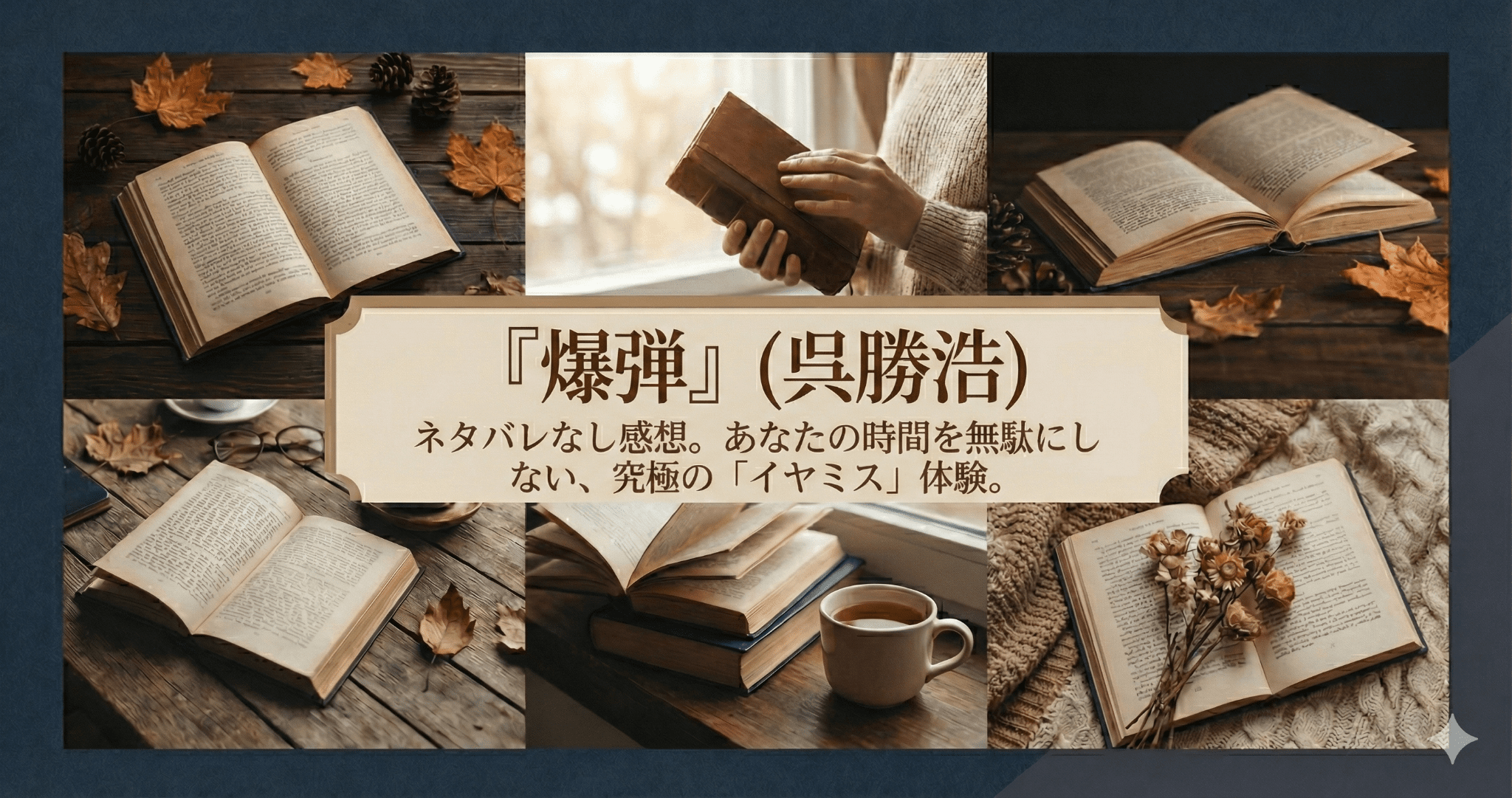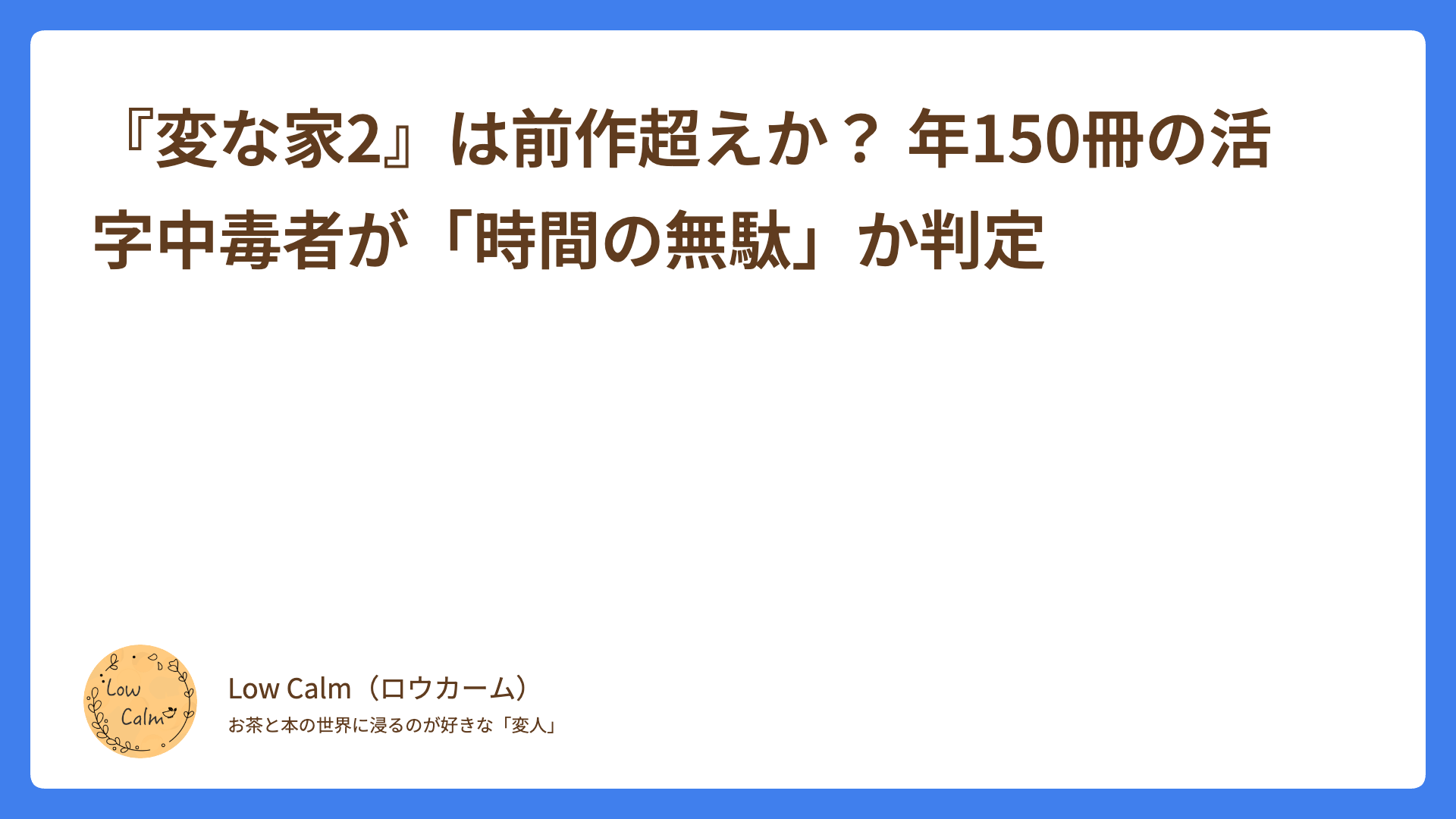『火のないところに煙は』芦沢央|ネタバレなし解説。「本の変人」が語る”違和感”の正体
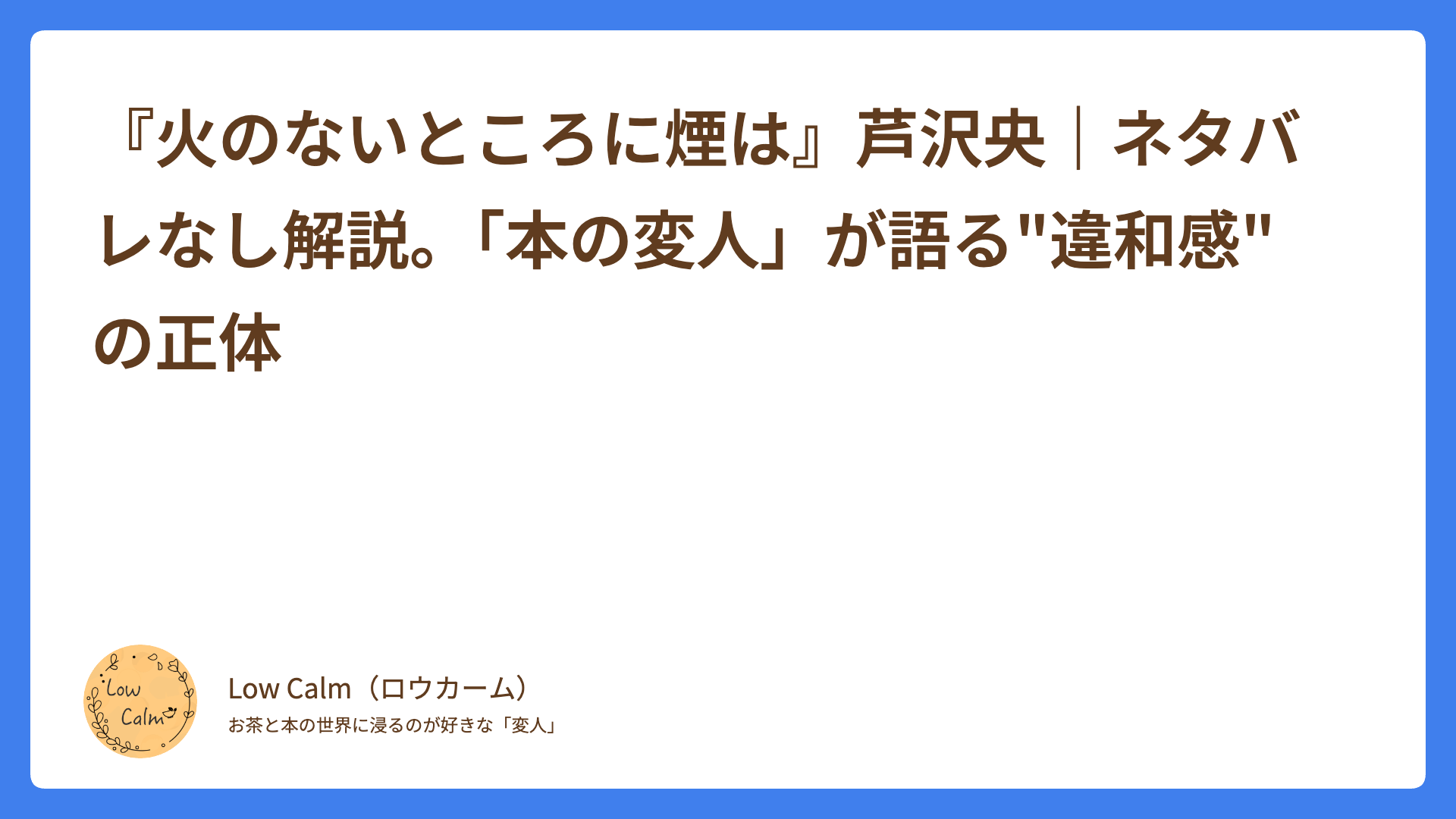
美味しいお茶を片手に本の世界に浸る時間、ようこそ、「本の変人」Low calm(ロウカーム)の書斎へ。
私のモットーは「あなたの時間を大切にすること」。 年間150冊ほどの本を読みますが、その中には当然「読む価値はなかった」と感じるものも含まれます。本選びの失敗ほど、人生において無駄な時間はありません。
だからこそ、このブログでは私が「これは!」と確信した良書、あるいは「これは避けるべき」と判断した本を、正直に紹介しています。
さて、今回取り上げるのは、芦沢央 氏の『火のないところに煙は』。
「怪談」と「ミステリ」が融合した、なんとも言えない不気味さを纏った一冊です。
「ただ怖いだけのホラーは飽きた」 「読んだ後、数日間引きずるような”嫌な感じ”が欲しい」 「スッキリ解決するより、解釈の余地がある物語が好き」
もしあなたが一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。
この記事では、ネタバレを一切せずに、以下の点を徹底的に解説します。
- 「本の変人」である私が「最高に気持ち悪い」と感じた魅力ベスト3
- 本書の「不気味さ」の正体
- あなたが本書を読むべきか、時間を無駄にしないために避けるべきかの最終判断
この記事を読み終える頃には、あなたがこの「煙」に巻かれるべきかどうかが、明確になっているはずです。
☕️ Low calmが選ぶ「グッときたところ」ベスト3
本書は、著者自身を思わせる「私」が、様々な人から怪異譚を聞き集めるという形式の連作短編集です。
一見バラバラに見える怪談が、読み進めるうちに細い糸で繋がり始め、やがて悍(おぞ)ましい全体像を浮かび上がらせます。
私が特に「やられた」と感じた、本作の核心に迫る魅力をご紹介します。
第3位:日常に潜む「違和感」の解像度の高さ
よくあるホラーのように、派手な幽霊やスプラッターは登場しません。 本書の怖さは、私たちが生きる日常に「染み」のようにこびりつく違和感です。
【グッときた箇所】 (特定の文章の引用ではなく、全体を貫く「雰囲気」について)
- 見慣れたはずの風景が、ほんの少しだけズレている感覚。
- 相手の言葉の端々に感じる、説明のつかない「引っかかり」。
- 「気のせい」で済ませてきた小さな異変。
【Low calmの考察】 これが本当に巧みです。恐怖とは、非日常からやってくるのではなく、日常の均衡が崩れた瞬間に生まれるのだと再認識させられます。
私は本業で人事労務の仕事をしていますが、人の「言葉」を扱う上で、この「違和感」には非常に敏感です。面談などで相手が何かを隠している時、あるいは本人も無自覚な本音を抱えている時、言葉の選び方や話の順序に奇妙な「ズレ」が生じます。
本書に登場する怪異も、この「ズレ」から始まります。 「火のないところに煙は立たない」ということわざがありますが、本書は「本当に火はなかったのか?」「その煙はどこから来たのか?」、あるいは「煙に見えるそれは、本当に煙なのか?」と、読者の認識そのものを揺さぶってきます。
この、現実が侵食されていくような、足元が崩れていくような感覚。これこそが、良質なホラーの第一条件です。
第2位:信頼できない「語り手」たち
本書は「私」が怪談を集める話ですが、その怪談を語る人々が、また曲者ぞろいです。
【グッときた箇所】 (各話の語り手の「姿勢」について)
- 「これは本当にあった話なんです」と前置きする人物。
- 自分に都合の悪い事実を、巧みに隠して語る人物。
- 恐怖体験を語りながらも、どこか他人事のような人物。
【Low calmの考察】 本書の構造は「怪談の取材」です。つまり、私たちは「怪談そのもの」と同時に、「怪談を語る人」をも見ることになります。
そして気づくのです。「この人、本当のことを言っているのか?」と。
人は誰しも、事実を「自分の解釈」というフィルターを通して語ります。そこには無自覚な(あるいは意図的な)嘘や誇張、記憶違いが必ず含まれます。
人事の仕事でも、「Aさんはこう言っていたが、Bさんは全く違う説明をする」という事態は日常茶飯事です。事実は一つでも、真実は人の数だけ存在する。
本書は、その「語り」の危うさ、人間の記憶の曖昧さを、ホラー・ミステリのギミックとして完璧に使いこなしています。 怖いのは怪異か、それとも人間か。 その境界線が曖昧になっていくプロセスは、まさに「イヤミス」好きの私にとって最高の”ご馳走”でした。
第1位:すべてが繋がった瞬間の「悪寒」と「突き放し」
そして、第1位。これこそが本書の真髄です。
【グッときた箇所】 (最終話、あるいは各話の「結末」の感覚について)
- 「え、そこで終わる?」
- 「あの話とこの話が、そう繋がるのか…」
- 「結局、”あれ”は、なんだったんだ?」
【Low calmの考察】 ネタバレ厳禁ゆえに詳細は語れませんが、バラバラだと思っていた短編が繋がり、一つの「真相」らしきものが見えた瞬間、私は「怖い」よりも先に「気持ち悪い」と感じました。
そして何より、芦沢氏は私たち読者に「明確な答え」を与えてくれません。
すべての謎が解け、犯人が捕まり、「ああ、スッキリした!」となるタイプのミステリではありません。 むしろ逆です。 読み終えた後、「あの描写の意味は?」「あの人物は結局どうなった?」「”私”は大丈夫なのか?」という無数の「?」が、読者の頭の中に残ります。
この「突き放し方」こそが、私が本書を「良書」と断言する最大の理由です。
スッキリしたいだけなら、他の本を読めばいい。 しかし、読了後も数日間、物語の「余韻」ならぬ「呪い」のようなものに思考を囚われたい。そんな「本の変人」にとって、この「解釈の余地」こそが、最高のエンターテインメントなのです。
🗣️ どんな人におすすめなのか
私の評価は「良書」ですが、万人に受けるとは到底思えません。 あなたの貴重な時間を無駄にしないため、読むべき人・避けるべき人を明確に提示します。
🙆 おすすめな人(時間を投資する価値アリ)
- 「イヤミス」のゾワゾワ感が好きな人 (湊かなえ氏や真梨幸子氏のような、読後に嫌な気持ちが残る作品が好きな方)
- 怪談・都市伝説の「背景」や「構造」に興味がある人 (「なぜその話が生まれたのか」を考察するのが好きな方)
- 明確な答えより「解釈の余地」を愛する人 (読後に「あれはどういう意味だったんだろう」と考えるのが好きな、私のような「変人」)
🙅 おすすめしない人(あなたの時間を無駄にします)
- 読後に「スッキリ爽快」な気分になりたい人 (本書は100%モヤモヤします。絶対に読まないでください)
- すべての伏線が回収される論理的な本格ミステリを求めている人 (これは怪異譚であり、論理ですべて割り切れる話ではありません)
- 「結局、よく分からなかった」という結末が許せない人 (その「分からなさ」こそが本作のキモなので、相性が最悪です)
📖 目次、著者プロフィール、本の詳細
本書の構造を理解するために、目次と書籍情報を確認しておきましょう。
目次
- 第一話 染み
- 第二話 お祓いを頼む女
- 第三話 妄言 第四話 助けてって言ったのに
- 五話 誰かの怪異 最終話 禁忌
(出典:新潮社公式サイト https://www.shinchosha.co.jp/book/350082/ )
著者プロフィール
芦沢 央(あしざわ よう) 1984年東京都生まれ。千葉大学文学部史学科卒業。出版社勤務を経て、2012年『罪の余白』で第3回野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。 著作に『悪いものが、来ませんように』『許されようとは思いません』『カインは言わなかった』など多数。ミステリ、イヤミス、ホラーなど、人間の暗部を鋭く描く作品で高い評価を得ている。
本の詳細
- タイトル: 火のないところに煙は
- 著者: 芦沢 央
- 出版社: 新潮社
- レーベル: 新潮文庫
- 発売日: 2021年6月24日
- ページ数: 288ページ
【Low calmの所感】
ご覧の通り、評価の分かれ目が「読後感」と「構造」に集中しています。
「スッキリしない」「意味がわからない」という否定的な意見は、まさに私が「グッときたところベスト1」で挙げた「突き放し方」そのものを指しています。
これは、本書が「合う人」と「合わない人」を明確に選ぶ、尖った良書である証拠です。 あなたがどちらのタイプか、これで判断がついたのではないでしょうか。
🔥 まとめ:「その違和感」を、あなたは信じますか?
最後に、この本が私に何をもたらしたかを記して、締めくくりとします。
【読む前の私】 「芦沢央氏の新作か。どうせまた、人が嫌な目にあうミステリだろう。怪談? まあ、おまけ程度かな」
【読んだ後の私】 「……気持ち悪い。これは怪談ではない。怪談を”語る”という行為そのものの不気味さを描いた、構造的ホラーだ。人の言葉がいかに信用できないか、そして日常の違和感を『気のせい』で済ませることが、いかに危ういか……」
本書を読んで、私は本業(人事)で人の話を聞く際、以前にも増して「この語りは、何を隠している?」と疑うようになりました。良い変化なのかは分かりませんが、確実に「解像度」が上がった感覚があります。
もしあなたが、 「グッときたところベスト3」で挙げた「違和感の正体」「信頼できない語り手」「突き放す結末」というキーワードに、少しでも心を掴まれたのなら。
そして、ただ消費されるだけのエンタメではなく、読んだ後もあなたの思考に侵食してくるような「毒」を求めているのなら。
『火のないところに煙は』は、あなたの時間を投資するに値する一冊です。
ぜひ、美味しいお茶でも淹れて、このじっとりとした「煙」に巻かれてみてください。 そして読み終えたら、私に教えてください。
あなたが感じた「違和感」の正体は、何でしたか?