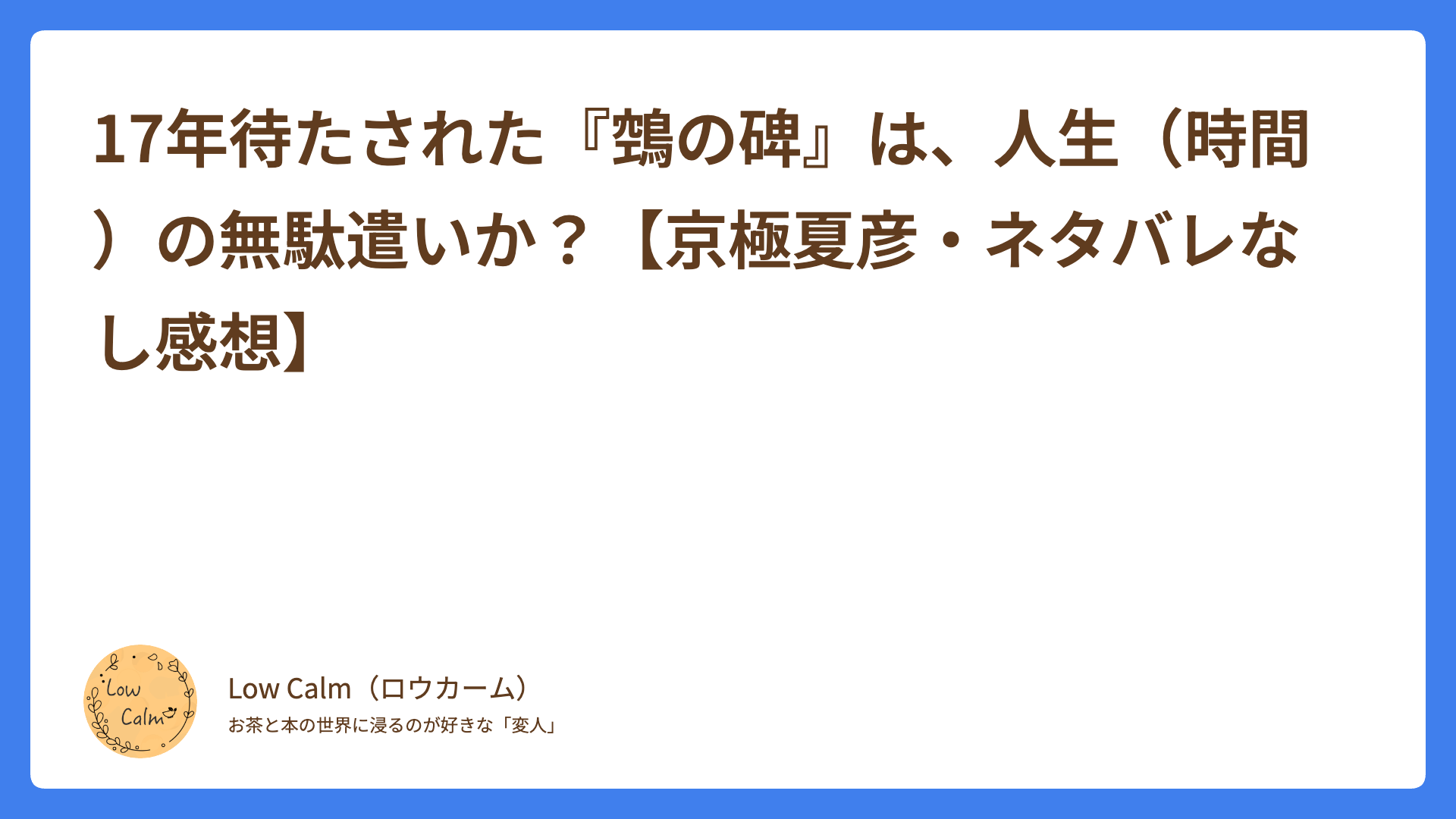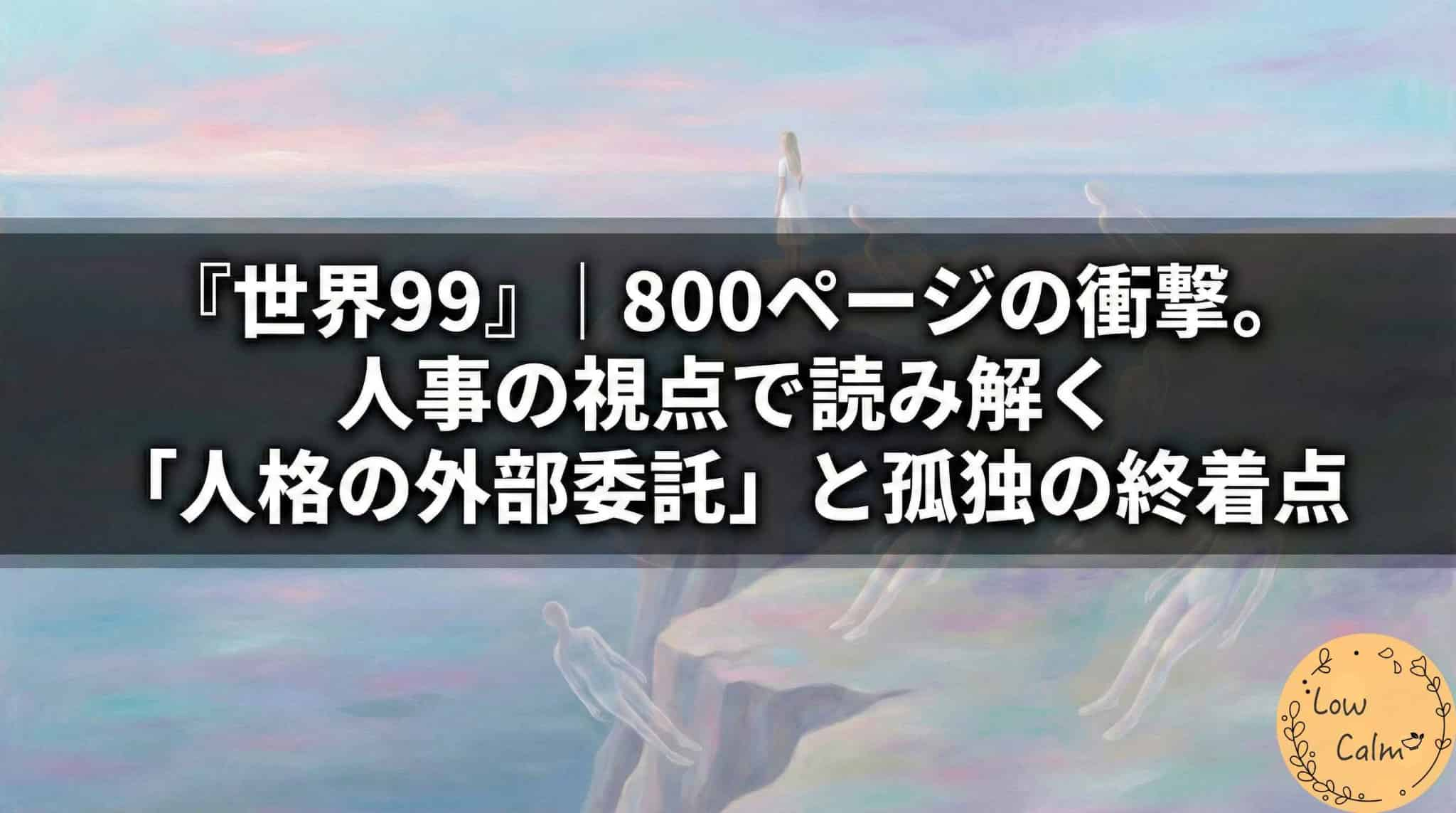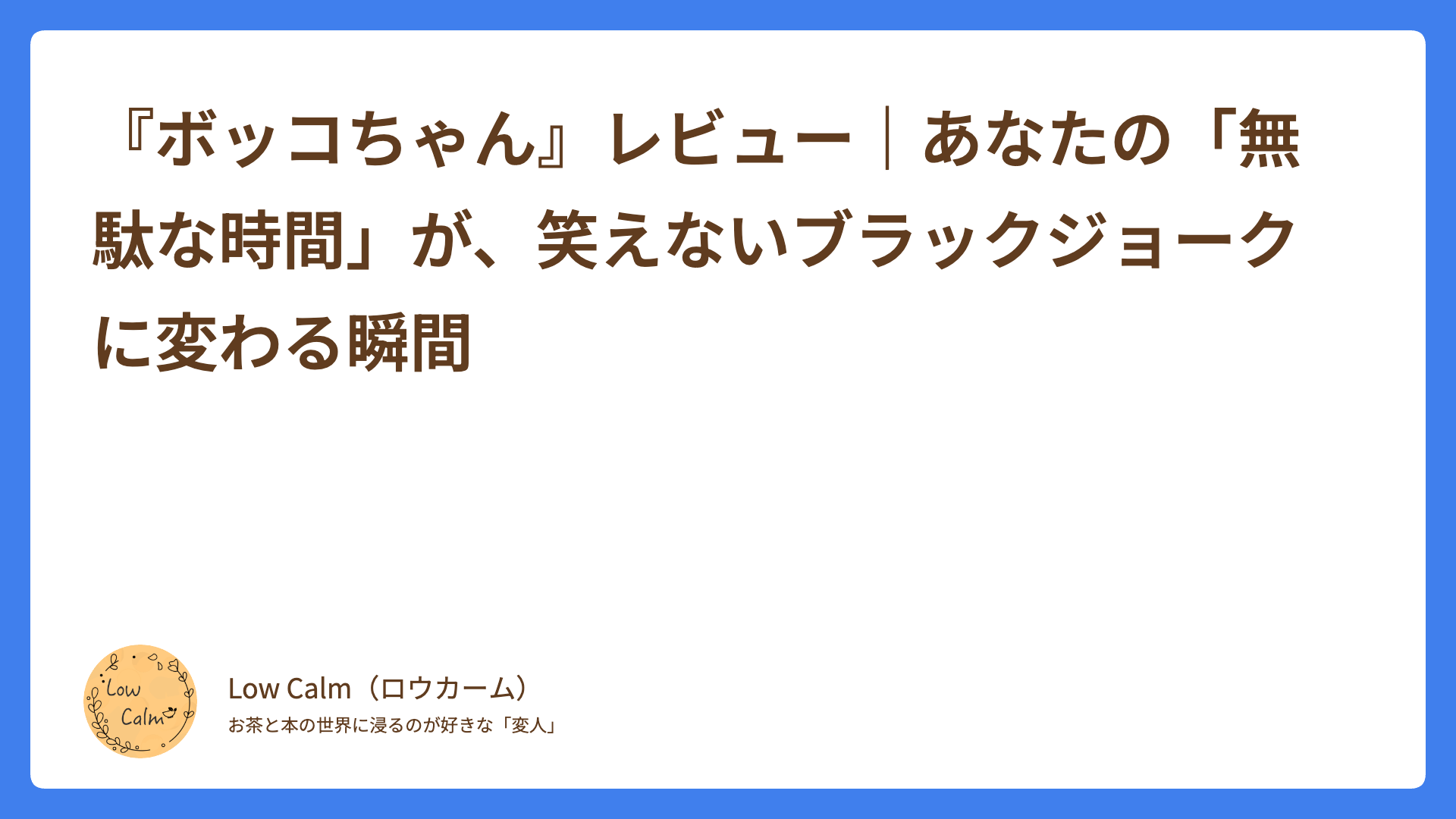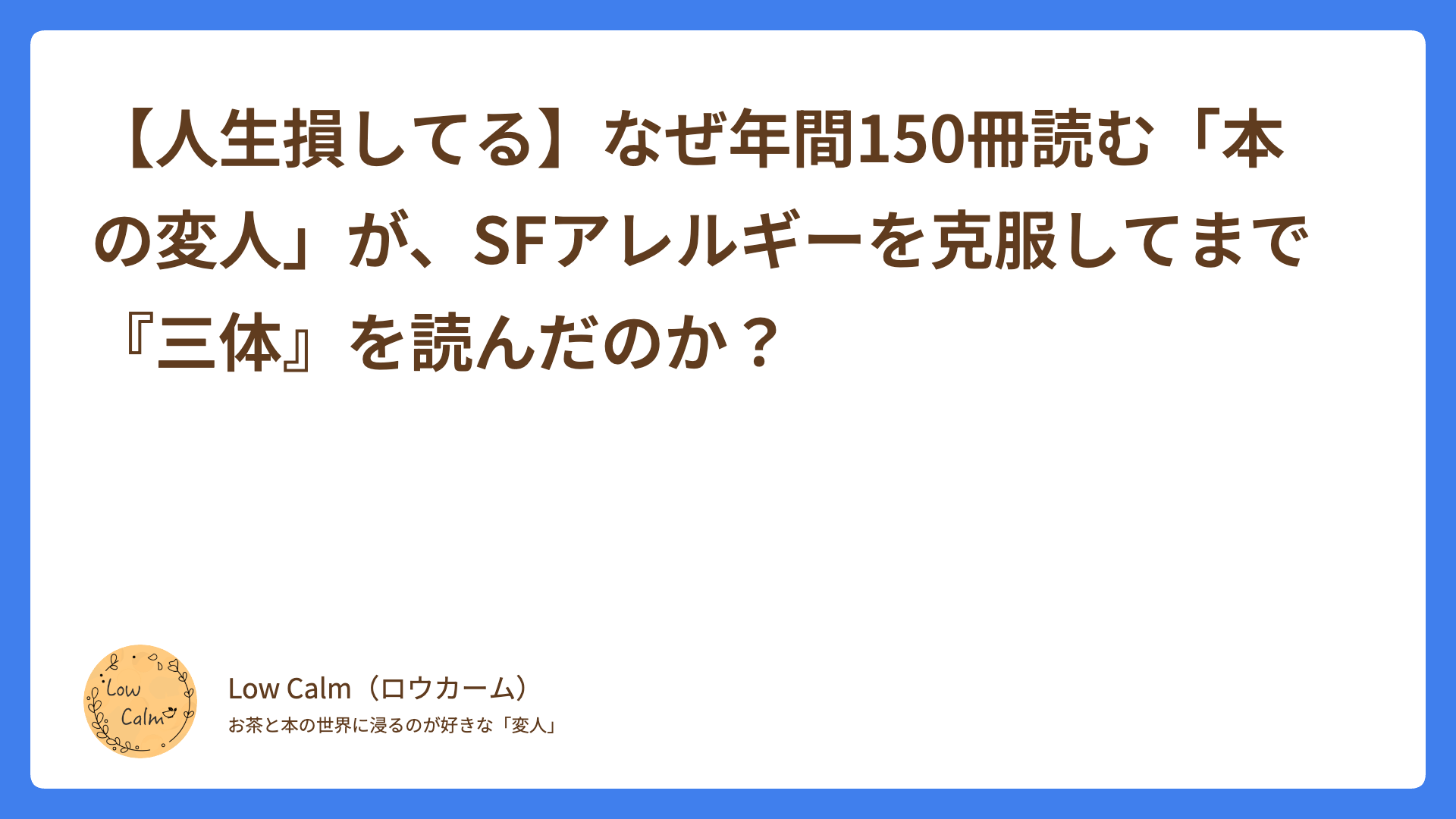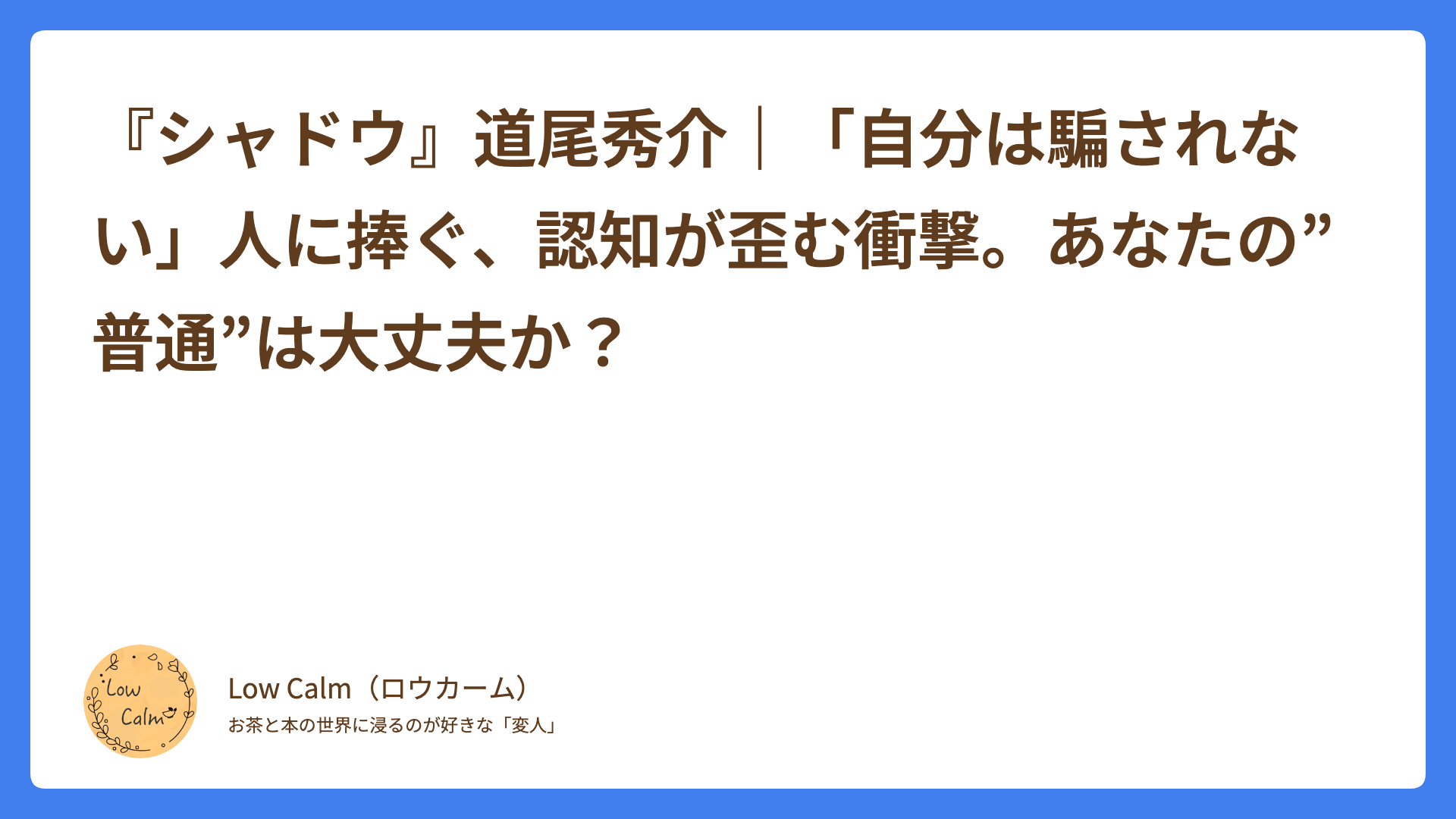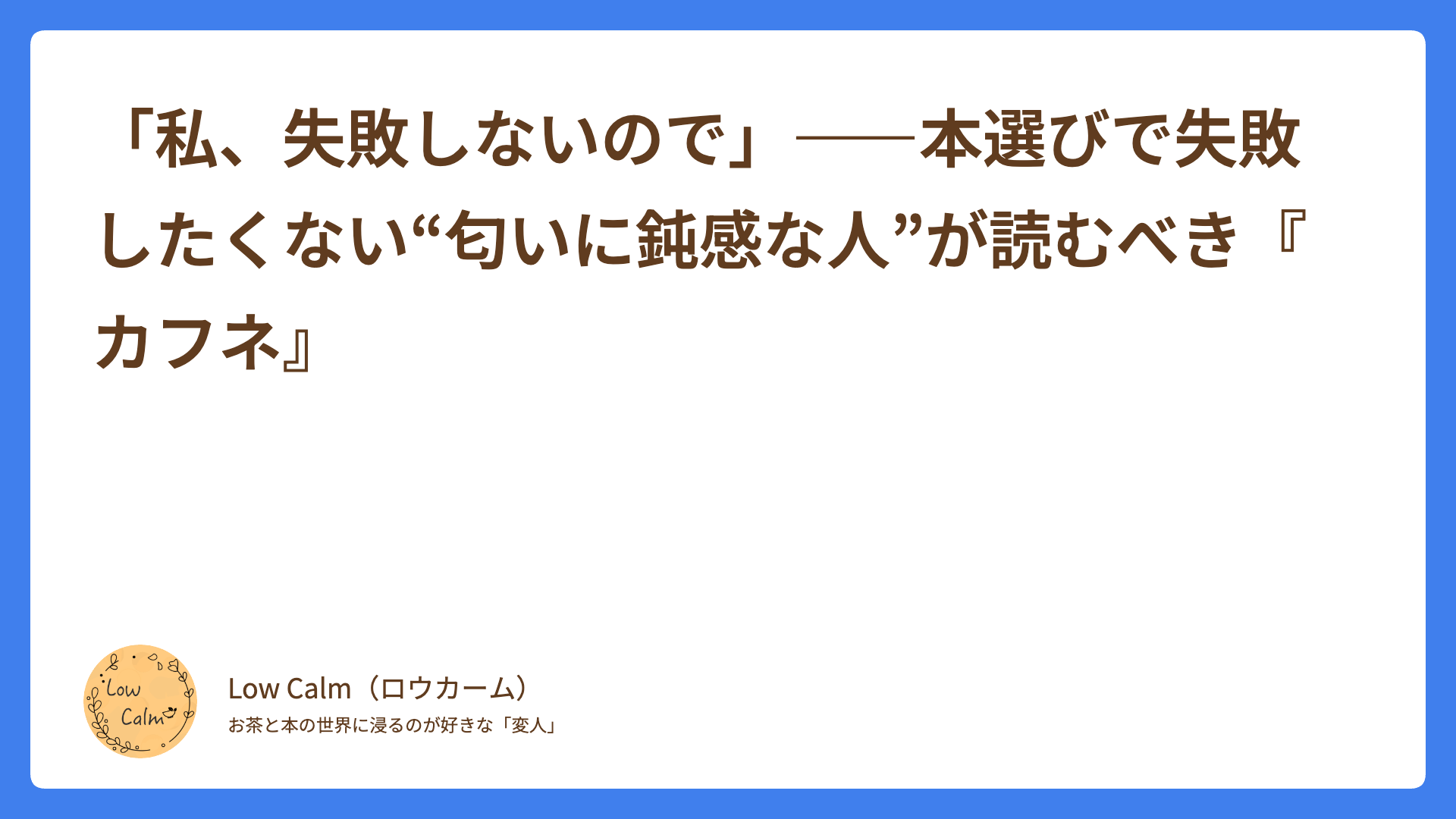もう「何者」にもなれないと焦るあなたへ。朝井リョウが暴く、巨大教会という名の現実。
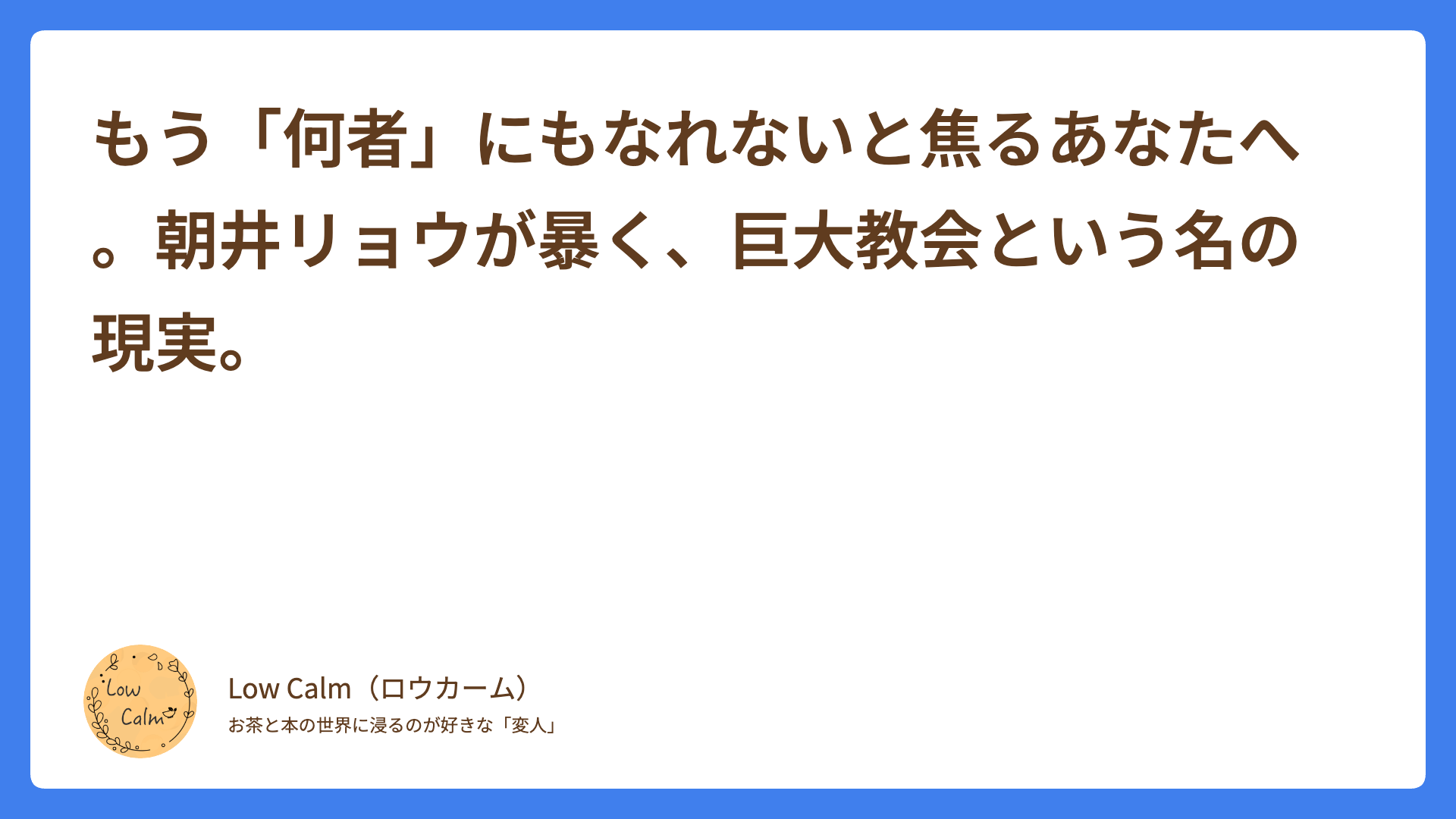
どうも、「本の変人」Low calm(ロウカーム)です。 美味しいお茶を淹れ、このブログを書き始めています。私のモットーは「あなたの時間を大切にすること」。私自身が「本選びの失敗」を心底嫌っており、このブログが、あなたが「失敗しない一冊」と出会う手伝いになれば幸いです。
先に結論を言います。
朝井リョウ氏の最新作『イン・ザ・メガチャーチ』は、現代社会という名の「巨大な教会(メガチャーチ)」の中で、承認と評価に飢え、自分を見失いかけている全ての人に突き刺さる、あまりにも誠実で、残酷な一冊です。
これは「推し活」小説ではありません。これは、あなたの、そして私の物語です。
この記事を読めば、「時間が無駄になるかもしれない」というあなたの懸念を3分で解消します。年間150冊の活字中毒者であり、特にイヤミスと純文学を愛する私が、「読むべきか、やめるべきか」をネタバレ一切なしで断言します。
この記事でわかること
- Low calmが本気で「グッときた」核心部分ベスト3(ネタバレなし)
- あなたが本書を読むべきか、時間の無駄になるかの判定リスト
- 本書の骨格(目次・詳細)と、世間の「本音」の口コミ
この記事を最後まで読めば、あなたが今所属しているコミュニティ(会社、SNS、友人関係)が、自分にとって本当に必要なものなのか、少しだけ冷静に見つめ直したくなるはずです。
☕️ Low calmがグッときたところベスト3
いつものように、私が最も心を揺さぶられた箇所を第1位から紹介します。ネタバレはしません。ただ、私がなぜそこを選んだのか、その理由と体験談を正直に記します。
第1位:「視野」を広げることが、必ずしも幸福に繋がらないという現実
私たちは幼い頃から「視野を広げろ」「多様な価値観を知れ」と教えられます。それは正しいことです。しかし、広げすぎた視野は、時に猛毒になります。
本書には、必死に視野を広げようと努める大学生、武藤澄香(むとう すみか)が登場します。彼女は真面目です。しかし、知れば知るほど、世の中の「正しさ」と「現実」の矛盾に気づき、動けなくなっていく。周囲が何かに熱狂し、盲目的になっている姿を、冷静に(あるいは冷ややかに)分析できてしまう。
その結果、どうなるか。 「熱狂」の輪から外れ、孤独になるのです。
これは、会社組織でも全く同じです。 私は本業で人事労務管理をしていますが、会社という「メガチャーチ」にも同じ構造があります。
会社の理念や方針(=教義)を疑わず、熱狂的に信じている(ように見える)社員は、コミュニティの中心にいます。一方、「この方針は本当に正しいのか?」「社会の潮流と逆行していないか?」と視野を広げ、客観的に分析してしまう社員は、時に「冷めている」「協調性がない」と評価され、疎外感を覚えていきます。
熱狂している側は、ある意味で幸せです。信じる「物語」があり、仲間がいるから。 しかし、その熱狂の外側に立ってしまった人間は、すべてを客観視できる代わりに、孤独という対価を支払わされる。
朝井リョウ氏は、その「孤独になっていく」人間の解像度があまりにも高く、読みながら「これは私のことだ」と何度も息を呑みました。あなたは、どちら側ですか?
第2位:「物語」を仕掛ける側の、恐ろしいほどの「誠実さ」
本作は、「推し活」や「ファンダム経済」と呼ばれる現象を、仕掛ける側からも描いています。 レコード会社に勤める久保田慶彦(くぼた よしひこ)は、アイドルグループの運営チームに加わり、いかにしてファン(=信徒)の熱量を高め、お金を使ってもらうかを設計します。
通常、このような「仕掛ける側」は、冷酷で打算的な「悪役」として描かれがちです。 しかし、朝井リョウ氏の筆致は違います。
彼らは、決してファンを騙そうとしているわけではない。むしろ、彼らは「本気で良い物語を提供しよう」と、驚くほど誠実なのです。ファンが何を求めているかを徹底的に分析し、彼らが求める「救い」や「熱狂」の“物語”を完璧にデザインして提供する。
ここに、本作の最大の「イヤミス」的要素があると私は感じました。
もし彼らが分かりやすい悪党なら、読者は「ひどい連中だ」と一線を引けます。しかし、彼らは誠実で、優秀で、ただビジネスとして「人の心を動かす」プロフェッショナルなのです。
これは、私たちが日常で触れる広告、マーケティング、あるいは社内政治にも通じます。 誰かを熱狂させ、動かすために作られた「物語」は、果たして本物か、偽物か。そして、その「物語」を提供する側は、悪意を持っているのか、それとも誠実な結果なのか。
その境界線が曖昧になっていく過程が、本当に恐ろしかった。純粋な悪意よりも、誠実な「システム」の方がよほど人を操れるという現実を、まざまざと見せつけられました。
第3位:「自分を使い切りたい」という焦燥感の正体
本作にはもう一人、重要な人物がいます。舞台俳優の「推し」に熱を上げていた、派遣社員の隅川絢子(くまがわ あやこ)です。彼女は、かつてその熱狂の中にいました。
なぜ人は、推し活や宗教、あるいは過度な仕事に「ハマる」のでしょうか。 その答えの一つとして提示されるのが、この「自分を余らせたくない」という感情です。
毎日が単調で、誰からも必要とされず、自分の能力や時間、あるいは情熱が「余っている」と感じる虚無感。 その虚無感を埋めるために、人は自分のリソース(時間、お金、情熱)を注ぎ込む対象=「物語」を探します。その対象がアイドルであれ、宗教であれ、陰謀論であれ、構造は同じです。
自分が「何者」でもないと焦る気持ち。 自分という存在を、どこかで「使い切りたい」という強烈な渇望。
朝井リョウ氏は、その渇望を抱える人間の心理を、まるで解剖するように丁寧に、執拗に描き出します。
人事労務の視点から見ても、この「渇望」は非常に重要です。 会社に異常なまでのめり込む(ワーカホリック)人も、もしかしたら「自分を使い切りたい」という焦燥感に駆られているのかもしれない。その熱狂が、会社という「メガチャーチ」への信仰になっていないか。
読みながら、私自身が「読書」という行為にのめり込むのも、もしかしたら「自分を余らせたくない」という焦燥感の表れではないかと自問し、背筋が寒くなりました。
📖 この本は、どんな人におすすめなのか
私のモットーは「あなたの時間を大切にすること」。万人に受ける本など存在しません。正直に、読むべき人・読むべきでない人を分類します。
おすすめな人(時間を投資する価値がある人)
- SNSや会社組織の「評価」に疲れ果てている人 「いいね」の数やフォロワー数、上司や同僚からの視線。そうした他者評価のシステムに息苦しさを感じているなら、本書はその「息苦しさ」の正体を言語化してくれます。
- 朝井リョウ氏の『何者』や『正欲』が好きな人 彼の作品特有の、人間の自意識やコミュニティ内の「空気」をえぐり出す作風が好きな方には、間違いなく刺さります。本作は、その「現代社会のえぐり方」がさらに進化したと感じました。
- 「推し活」や「信仰」の構造を客観的に知りたい人 なぜ人は何かに熱狂するのか。その熱狂はどこから来て、どこへ行くのか。そのメカニズムを、仕掛ける側・ハマる側・冷めた側の三者から冷静に知りたい知的好奇心のある方。
おすすめしない人(時間の無駄になる可能性が高い人)
- 読書に「スカッとする快感」や「明確な救い」だけを求める人 本書はイヤミス(読んだ後に嫌な気持ちになるミステリ)的な側面が強く、明確なハッピーエンドや「これで解決!」というカタルシスは提供してくれません。現実を突きつけられる重さがあります。
- 人間の暗い感情や、ドロドロした部分を読むのが苦手な人 嫉妬、焦燥感、孤独、承認欲求。人間のネガティブな感情がこれでもかと描かれます。心が弱っている時に読むと、引きずられる可能性があります。
- 宗教や「推し活」というテーマ自体に強い嫌悪感がある人 テーマ自体が生理的に受け付けない場合、本書の核心に触れる前に読むのが苦痛になるかもしれません。これは「推し活」の是非を問う本ではなく、それを構造として利用した人間ドラマです。
📚 目次、著者プロフィール、本の詳細
本の目次構成について
本書は、久保田慶彦(47歳)、武藤澄香(19歳)、隅川絢子(35歳)という3人の主要人物の視点が、章ごとに入れ替わりながら進む群像劇です。
全14章以上の構成ですが、各章のタイトルをここに羅列することは、かえって読書体験の純度を下げる(あるいはネタバレに繋がりかねない)と私は判断しました。
Low calmのポリシーとして、本はまっさらな状態で読む時間こそを大切にしていただきたい。そのため、ここでは詳細な目次の記載を割愛します。ただ、3人の視点が交錯し、一つの巨大な「教会」の姿が浮かび上がってくる構成である、とだけお伝えしておきます。
(出典元:日経BP 日本経済新聞出版 書籍紹介ページ) https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784296121045
著者プロフィール
朝井 リョウ(あさい りょう) 1989年、岐阜県生まれ。小説家。 早稲田大学在学中の2009年、『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2013年、『何者』で第148回直木三十五賞を、戦後最年少(当時)、平成生まれとして初めて受賞。2021年、『正欲』で第34回柴田錬三郎賞を受賞。 他の著書に『世界地図の下書き』『スター』『生殖記』、エッセイ集『時をかけるゆとり』など多数。現代社会に生きる人々の自意識や関係性を鋭く描き出す筆致に定評がある。
本の詳細
- タイトル: イン・ザ・メガチャーチ
- 著者: 朝井 リョウ
- 出版社: 日経BP (日本経済新聞出版)
- ページ数: 448ページ
- 発売日: 2025年9月3日
- 価格: 2,200円(税込)
🏁 まとめ:あなたは、どの「教会」に所属しますか?
あらためて、私が本作で「グッときた」3つのポイントを振り返ります。
- 視野を広げた人間から孤独になるという現実
- 物語を仕掛ける側の、誠実さという名の恐ろしさ
- 「自分を余らせたくない」という焦燥感の正体
これら3つをつなげると、本書の核心が見えてきます。
それは、「私たちは皆、何かしらの“物語”を信じなければ生きていけないほど弱く、そして、その“物語”を提供する『教会(=システム)』に、知らず知らずのうちに飼いならされている」という現実です。
その「教会」とは、会社かもしれないし、SNSの「界隈」かもしれません。あるいは、国家や家族というシステムそのものかもしれない。
本書を読んだ私自身の変化(ビフォーアフター)を告白します。 読む前は、私にとって「読書」は純粋な娯楽であり、知的な趣味でした。しかし読んだ後、私(Low calm)が年間150冊も本を読み漁り、こうしてブログを書いている行為自体が、「本の変人」という「物語」に所属することで、社会における孤独や虚無感から目をそらしているだけではないか、という疑念が生まれました。
私は、私自身が所属する「読書」という名のメガチャーチに、気づかされたのです。
だからこそ、この記事を読んだあなたへの具体的なアクションプランを提案します。
まず、あなたが今、熱狂的に所属している「教会」が何なのかを自問してみてください。
それは、本当にあなたの人生を豊かにしていますか? それとも、あなたの時間や情熱を「搾取」しているだけではありませんか?
『イン・ザ・メガチャーチ』は、その自問へのヒントをくれる、冷徹で、しかし誠実な「鏡」のような一冊です。あなたの時間を投資する価値があるか、その判断材料になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 あなたの貴重な時間をいただき、感謝します。