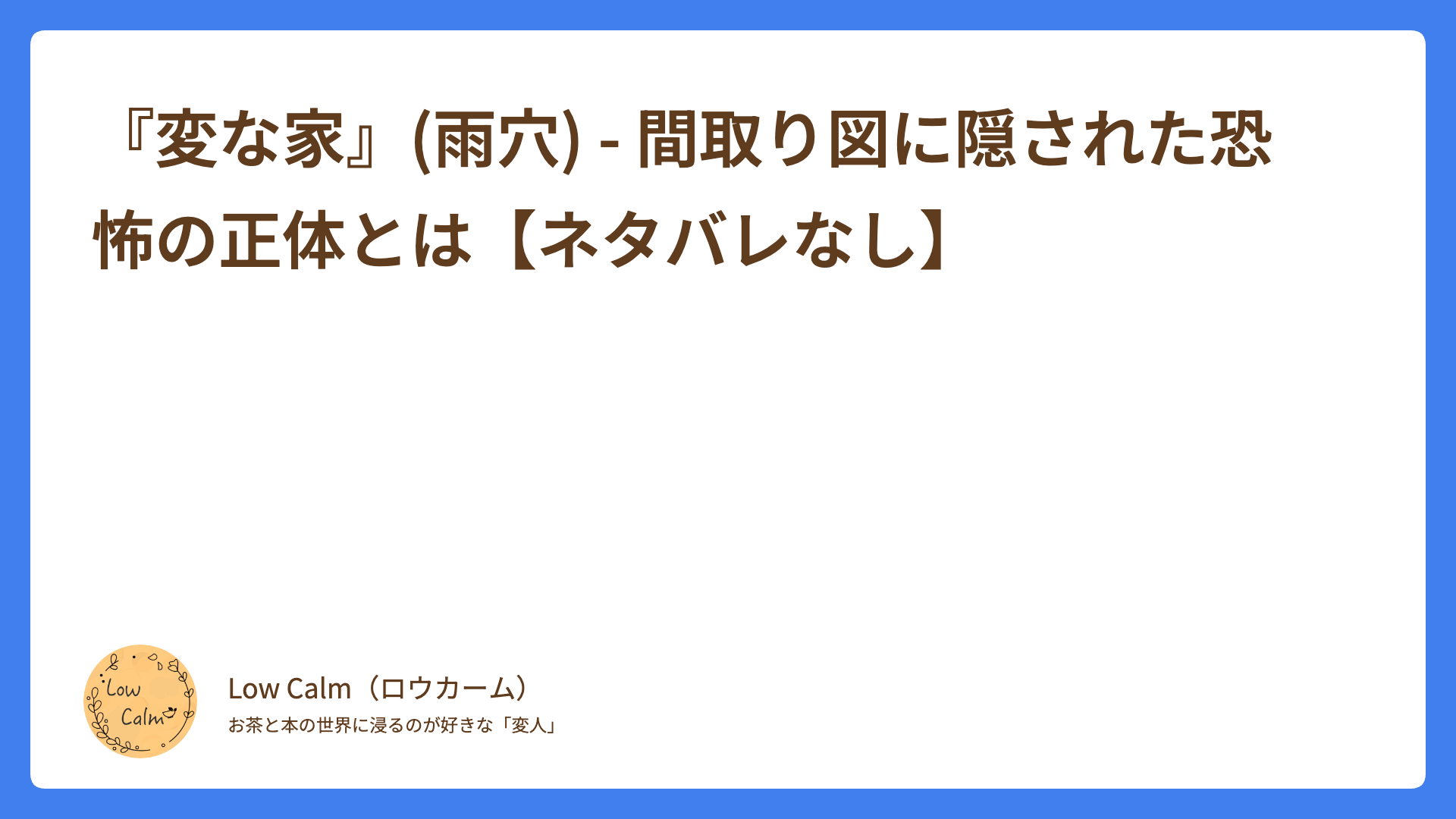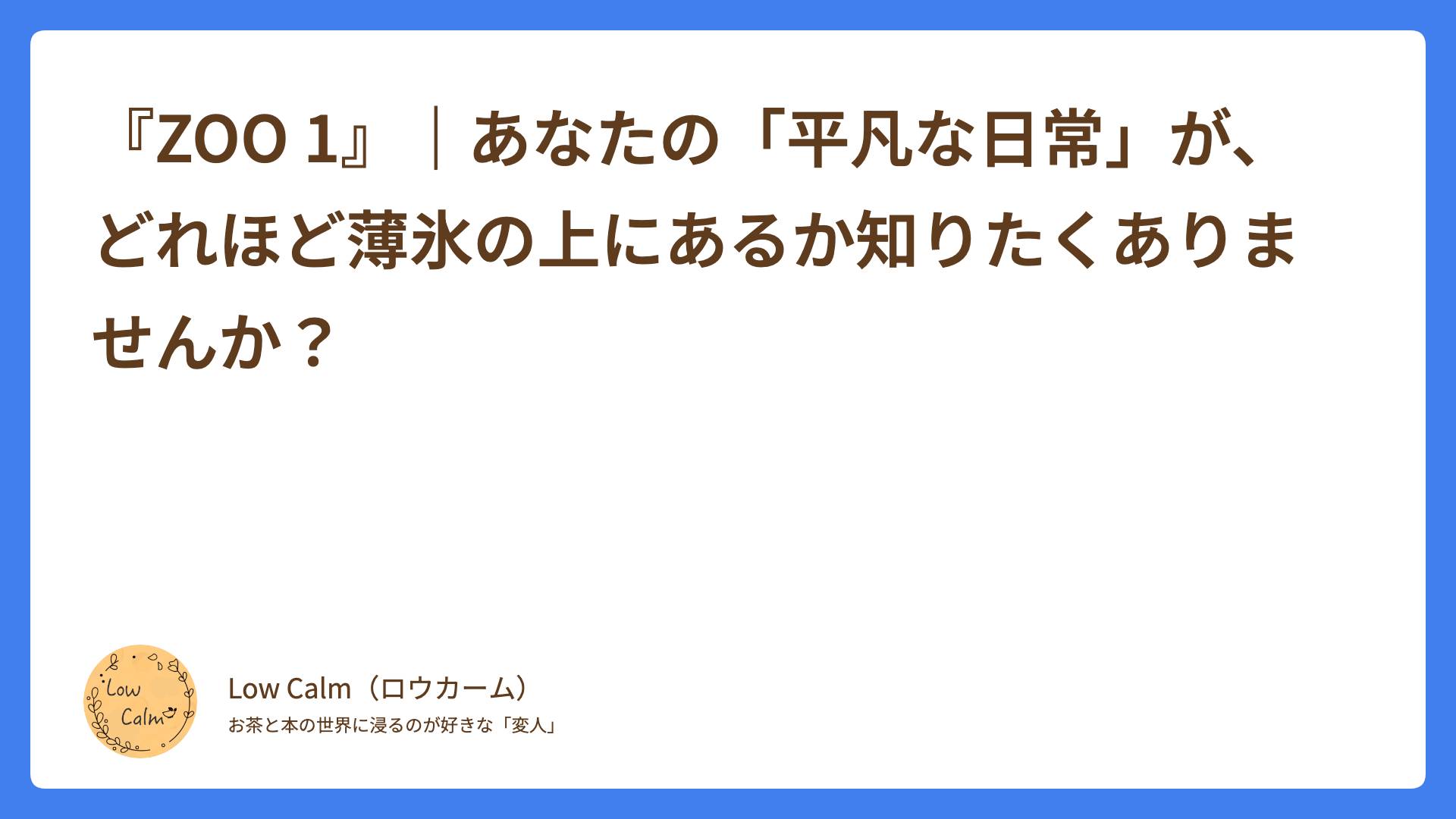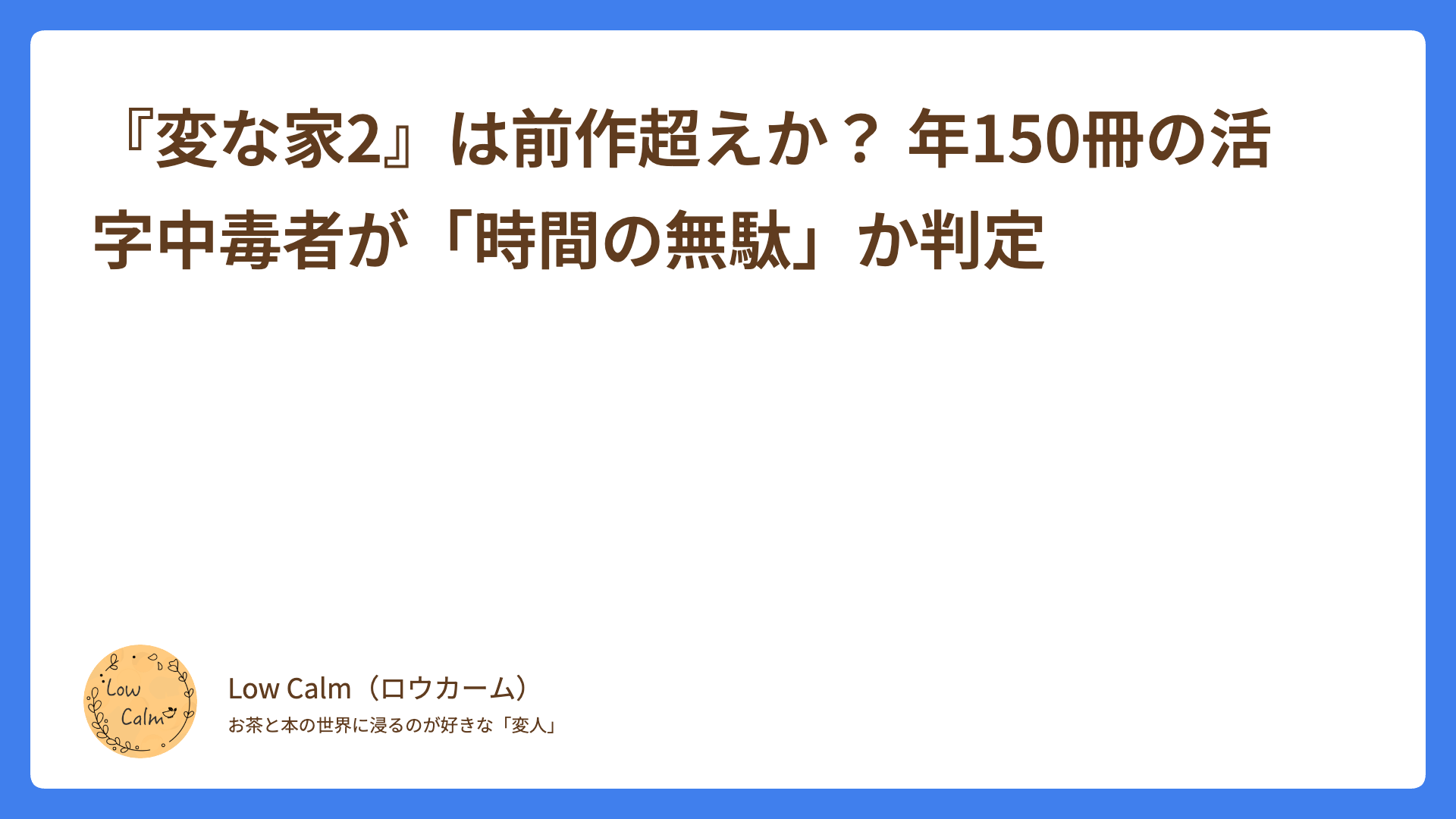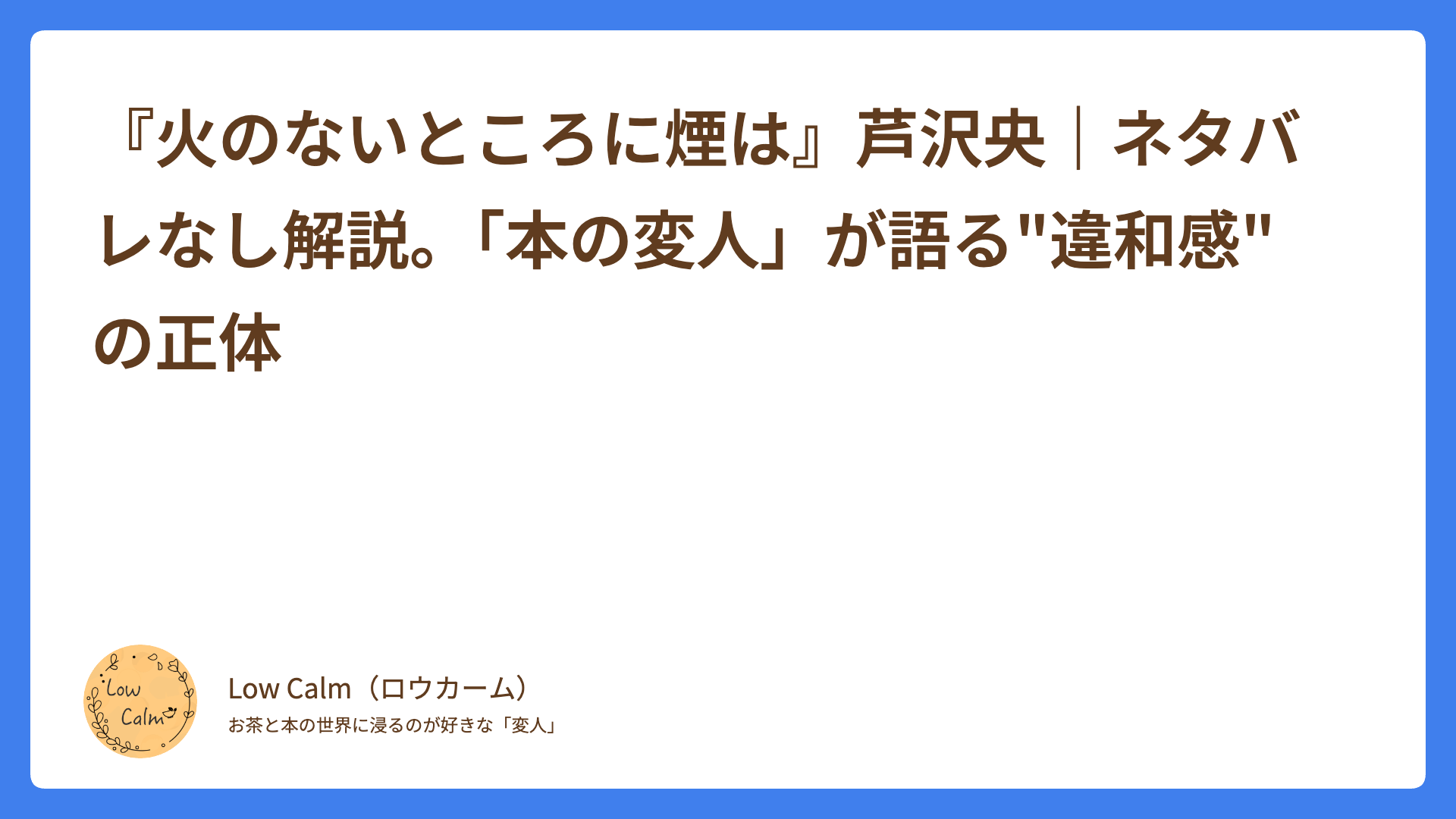『殺戮にいたる病』は時間の無駄か?「本の変人」が警告する、絶対に結末を知ってはいけない衝撃【ネタバレなし】
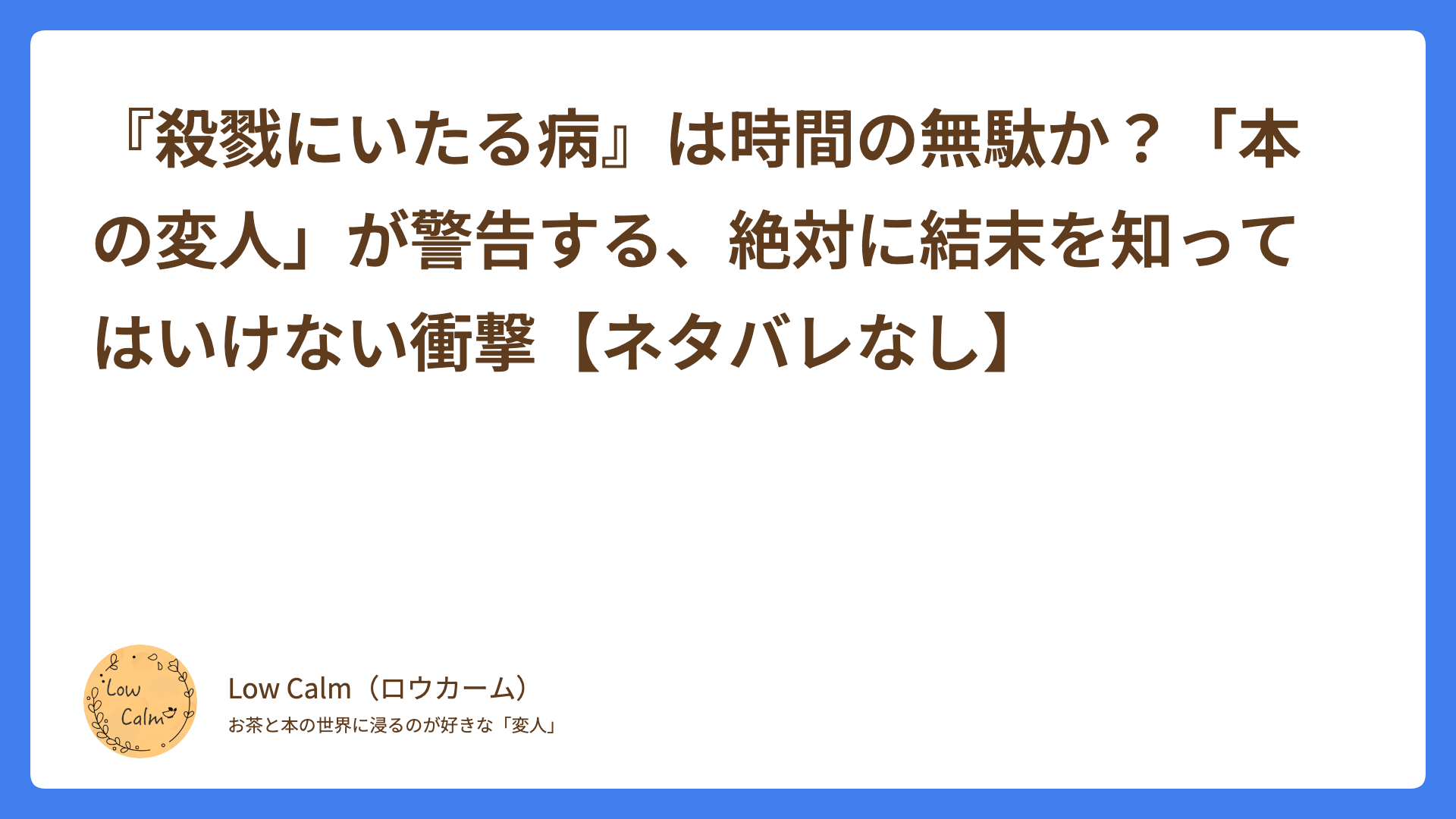
どうも、こんにちは。「本の変人」ことLow calm(ロウカーム)です。 美味しいお茶を淹れ、今日も書棚と向き合っています。
私のモットーは「あなたの時間を大切にすること」。 年間150冊ほどの本を読みますが、その中には当然「これは時間の無駄だった」と感じる本も(悲しいことに)存在します。本選びの失敗は、時間と精神の両方を削る行為です。
だからこそ、このブログでは、私が「これは!」と確信した本、あるいは「これは警告が必要だ」と感じた本だけを、正直に紹介しています。
さて、今回取り上げるのは、我孫子武丸氏の『殺戮にいたる病』。
ミステリ好きの間では「伝説」「金字塔」と呼ばれ、「絶対に結末を先に読んではいけない」「人生で一度きりの衝撃」とまで言われる作品です。
しかし、同時に「グロテスクすぎる」「気分が悪くなる」という声も多く、本棚の前で手に取っては戻す…を繰り返している方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんなあなたのために、「本の変人」であり、特に「イヤミス(読後に嫌な気分になるミステリ)」を愛好する私の視点から、以下の点を一切のネタバレなしで徹底的に解剖します。
- この記事でわかること:
- 本書が「伝説」と呼ばれる「本当の理由」(ネタバレなしで核心に迫ります)
- 私が心を掴まれた「グッときたところ」ベスト3
- あなたが本書に貴重な時間を投資すべきか否かの最終判断(おすすめな人・しない人)
- この記事の信頼性:
- 年間150冊の読書家であり、ミステリを愛する私が、あなたの「本選びの失敗」を防ぐために全神経を集中させて執筆します。
- この記事を読んだ後のあなた:
- 『殺戮にいたる病』が、あなたにとって「読むべき一冊」なのか、それとも「避けるべき一冊」なのか、明確な答えが出ているはずです。
あなたの貴重な読書時間を、最高の一冊(あるいは最悪の一冊)のために使う準備はよろしいでしょうか。
🫀 グッときたところベスト3(ネタバレなし)
この作品は、その性質上、具体的な文章の引用が非常に難しい。物語の核心に触れずに魅力を伝えるため、私が心を揺さぶられた「体験」そのものをランキング形式でお届けします。
第3位:「日常」と「異常」の境界線を曖昧にする生々しい筆致
本書は、ある猟奇的な連続殺人犯の視点と、その周囲の人物たちの視点が交錯しながら進みます。
特に強烈なのが、犯人である「蒲生稔」のパート。彼の内面、思考、そして実行に至るプロセスが、恐ろしいほど冷静かつ詳細に描かれます。
私が本業(会社員・人事労務)で日々接しているのは、良くも悪くも「普通」の人々です。しかし、本書を読んでいると、「普通」と「異常」の境界線がどこにあるのか、わからなくなってくるのです。
グッときた箇所(の概要): 犯人が、自身の異常な欲望を「愛の探求」という極めて個人的な論理で正当化していく過程。
なぜグッときたか: 彼は決して、生まれながらの怪物として描かれているわけではありません。彼の中には、私たちにも理解できてしまうかもしれない「孤独」や「渇望」の断片が隠されています。
人事労務として何百人という「普通」の顔を見てきた私だからこそ、その「普通」の仮面の下に、どれほど深い闇が隠れている可能性があるのか、という現実にぞっとさせられました。この生々しい描写こそが、単なる猟奇小説で終わらせない、本書の凄みの一つです。
第2位:読者を「共犯者」にする、計算され尽くした構成
本書は、複数の視点と時系列が巧みに組み合わされて進行します。 (詳細は「目次」のセクションで後述します)
読者は、犯人「稔」、彼の行動を疑う母「雅子」、事件を追う元刑事「樋口」の3人の視点を、目まぐるしく行き来することになります。
グッときた箇所(の概要): 読者が「この視点はこういうことだろう」と自然に思い込み、物語のピースを組み立ててしまうように誘導する、巧みな情報の提示順序。
なぜグッときたか: ミステリ好きを公言する私は、「作者の仕掛けなどお見通しだ」と、ある種、驕った気持ちで読み始めました。しかし、読み進めるうちに、自分がいかに作者・我孫子武丸氏の掌の上で踊らされているかを痛感したのです。
作者は、読者が「こうに違いない」と推測する心理を完璧に読み切っています。私たちは、情報を追ううちに、いつの間にか物語の「共犯者」となり、自ら「誤った結論」へと突き進んでしまう。この「騙される(あるいは、自ら騙されにいく)感覚」こそ、上質なミステリだけが提供できる最高のエンターテインメントです。
第1位:「読書体験」そのものを根底から覆す、あの「仕掛け」
第1位は、これしかありません。 もちろん、具体的なことは一文字たりとも書けません。それが、この本に対する最大の敬意であり、これから読むあなたの時間を守るための、私からの約束です。
グッときた箇所: (秘密です)
なぜグッときたか: 「あなたの時間を大切にしたい」 私は、本選びの失敗を心底嫌っています。
本書は、ハッキリ言って強烈な不快感を伴う描写に満ちています。もし、この衝撃的な「仕掛け」がなかったとしたら、私はこの記事で「読む価値なし。あなたの時間の無駄だ」と断言していたでしょう。
しかし、あの「仕掛け」を体験した瞬間、それまでの不快感、グロテスクな描写、すべてがこの一点のために存在していたのだと理解し、私は文字通り、本を閉じて数分間、呆然としました。
これは単なる「どんでん返し」ではありません。 読者であるあなた自身が、これまで読んできた「すべて」を疑い、もう一度最初からページをめくり直したくなる、という強烈な体験を強制する「仕掛け」です。
年間150冊読む私でも、これほどの衝撃を受けたのは数えるほどしかありません。 この「体験」のためだけに、あなたは『殺戮にいたる病』に時間を投資する価値があると、私は断言します。
👥 どんな人におすすめなのか
この本は、劇薬です。万人に勧められるものでは断じてありません。 あなたの貴重な時間を守るため、ハッキリと「おすすめな人」と「おすすめしない人」を提示します。
🙆 おすすめな人
- 「騙される快感」を何よりも愛するミステリ上級者 「どんでん返し」と名の付く作品は読み尽くした、という方にこそ挑戦してほしい一冊です。あなたのミステリ偏差値が試されます。
- 「イヤミス」が大好物で、読後に嫌な気分(褒め言葉)になりたい人 癒しや感動など微塵もありません。むしろ、人間の最も暗く、グロテスクな部分を直視したいという(私のような)歪んだ欲望を持つ方には、これ以上ないご馳走です。
- 「伝説」と呼ばれる作品の「答え」を、自分の目で確かめたい人 なぜこの本が30年近く経っても語り継がれるのか。その理由を知る「体験」は、他の何にも代えがたいものです。
🙅 おすすめしない人
- 読書に「癒し」「感動」「心温まる結末」を求める人 絶対に読んではいけません。 あなたの時間を100%無駄にします。読後は確実に気分が沈みます。別の素晴らしい本(例えば、心洗われる純文学や、痛快なエンタメ小説)を読みましょう。
- 猟奇的な描写、グロテスクな表現が本当に苦手な人 本書の描写は生半可ではありません。かなり直接的かつ詳細に描かれています。食事中に読むなどは論外です。少しでも不安があるなら、迷わず避けてください。
- ミステリの「トリック」よりも、登場人物の「人間ドラマ」を重視する人 本書の魅力は、その精巧な「仕掛け」に極度に依存しています。もちろん登場人物の心理描写はありますが、それは全て「仕掛け」のためのパーツです。深い人間愛や成長の物語を期待してはいけません。
📖 目次(構成)、著者のプロフィール、本の詳細
本書の魅力を理解する上で、その「構造」を知ることは非常に重要です。
目次(本書の構成)
本書には、一般的な小説のような「第一章」「第二章」といった章立てはありません。 まず「エピローグ」から始まり、その後、以下の3人の視点が、時系列を交錯させながら入れ替わっていきます。
- 稔(みのる): 猟奇殺人を繰り返す犯人
- 雅子(まさこ): ある人物の行動を疑い、恐怖に苛まれる女性
- 樋口(ひぐち): 事件の異様さに気づき、独自に調査する元刑事
この「誰の視点」で「いつの時点」が描かれているのかを意識することが、本書の「仕掛け」を解き明かす(あるいは、見事に騙される)ための鍵となります。
(※講談社BOOK倶楽部およびAmazonの書籍情報ページを参照しました)
著者のプロフィール
我孫子 武丸(あびこ たけまる) 1962年、兵庫県生まれ。京都大学文学部中退。 在学中は「京都大学推理小説研究会」に所属。1989年、『8の殺人』で作家デビュー。 『殺戮にいたる病』のほか、『探偵映画』『弥勒の掌』などの重厚なミステリから、「速水三兄妹」シリーズのようなユーモラスな作品まで、多彩な作風で知られる。 また、大ヒット推理ゲーム『かまいたちの夜』のシナリオを手掛けたことでも非常に有名。
『かまいたちの夜』で彼の名前を知った方も多いでしょう。あのゲームでプレイヤーを恐怖と混乱に陥れたシナリオライターが、小説で本領を発揮したのが本作、と聞けば、その「ヤバさ」が伝わるでしょうか。
本の詳細
- タイトル: 殺戮にいたる病(新装版)
- 著者: 我孫子 武丸
- 出版社: 講談社文庫
- 発売日: 1996年11月15日(※オリジナル単行本は1992年)
- ページ数: 324ページ
🏁 まとめ:あなたの時間を投資する「覚悟」はありますか?
さて、長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。 『殺戮にいたる病』がどのような本か、その毒素と魅力が伝わったでしょうか。
最後に、「本の変人」Low calmとして、本書を総括します。
本書の核心は、「グッときたところベスト3」で挙げた「日常に潜む異常」「読者を共犯者にする構成」そして「すべてが反転するあの仕掛け」、この3つが完璧に連動している点にあります。
この本を読んだことによる私の変化(ビフォーアフター)を述べるならば、 「ミステリの『仕掛け』は、ここまで読書体験を支配できるのか」 という、ミステリというジャンルそのものへの畏敬の念を再確認させられました。
あなたの時間を大切にする私から、最後の問いかけです。
あなたは、強烈な不快感を覚えるリスクを負ってでも、人生で一度きりかもしれない「読書体験の衝撃」を選びますか?
もし、その覚悟が決まったのなら、今すぐ本書を手にとってください。 そして、あなたに唯一つ、私からのお願いがあります。
もし読むと決めたなら、読み終わるまで、絶対に、絶対に、他の感想やレビュー(この記事のコメント欄も含む)を検索しないでください。
まっさらな状態で、たった一人で、この「病」と向き合うこと。 それこそが、我孫子武丸氏が仕掛けたこの恐ろしい傑作を、最高(あるいは最悪)の形で味わう、唯一の方法なのですから。
あなたの読書時間が、失敗しない一冊と出会う時間となりますように。
それでは、また次の「これは!」という本でお会いしましょう。Low calmでした。