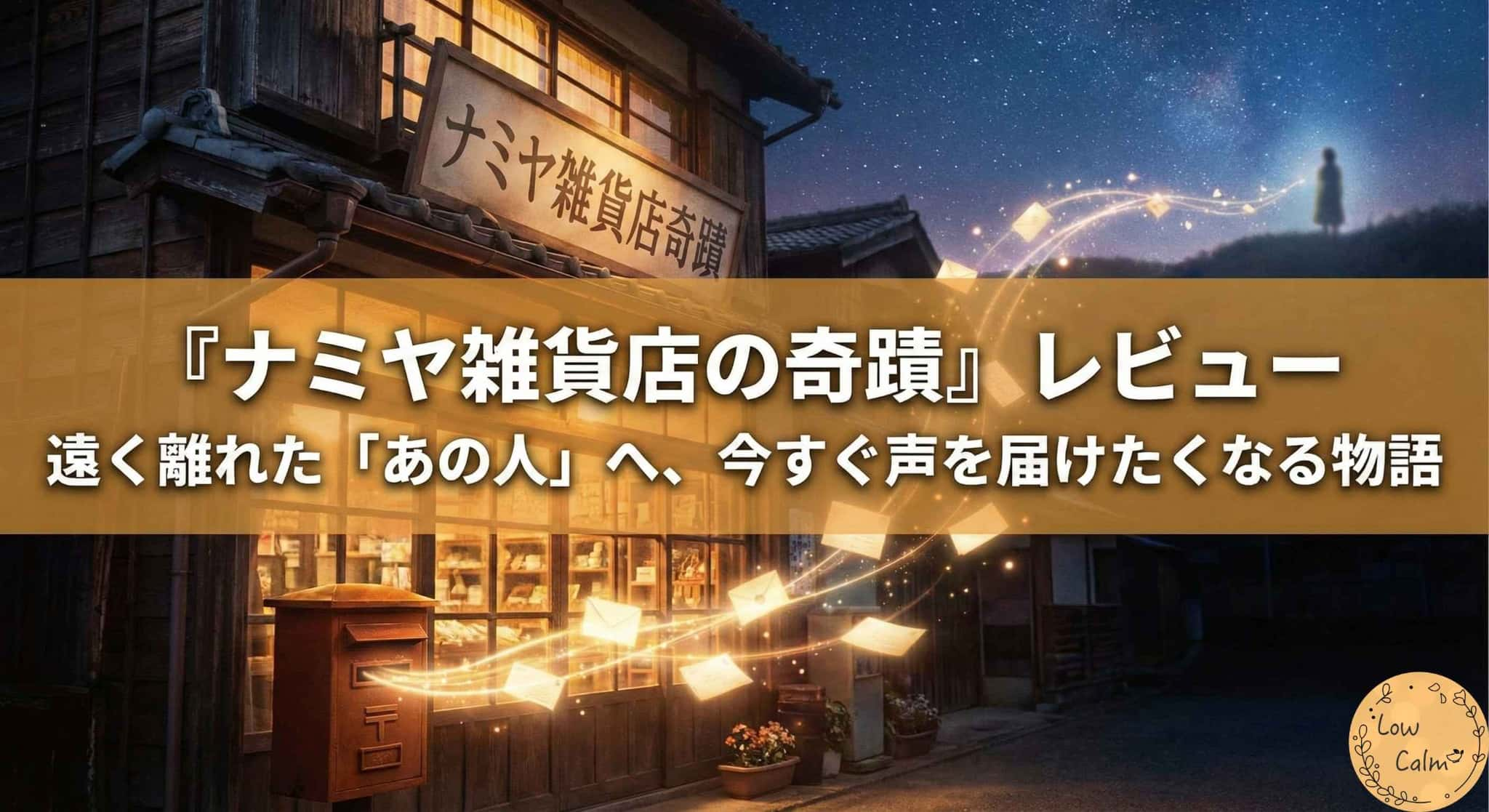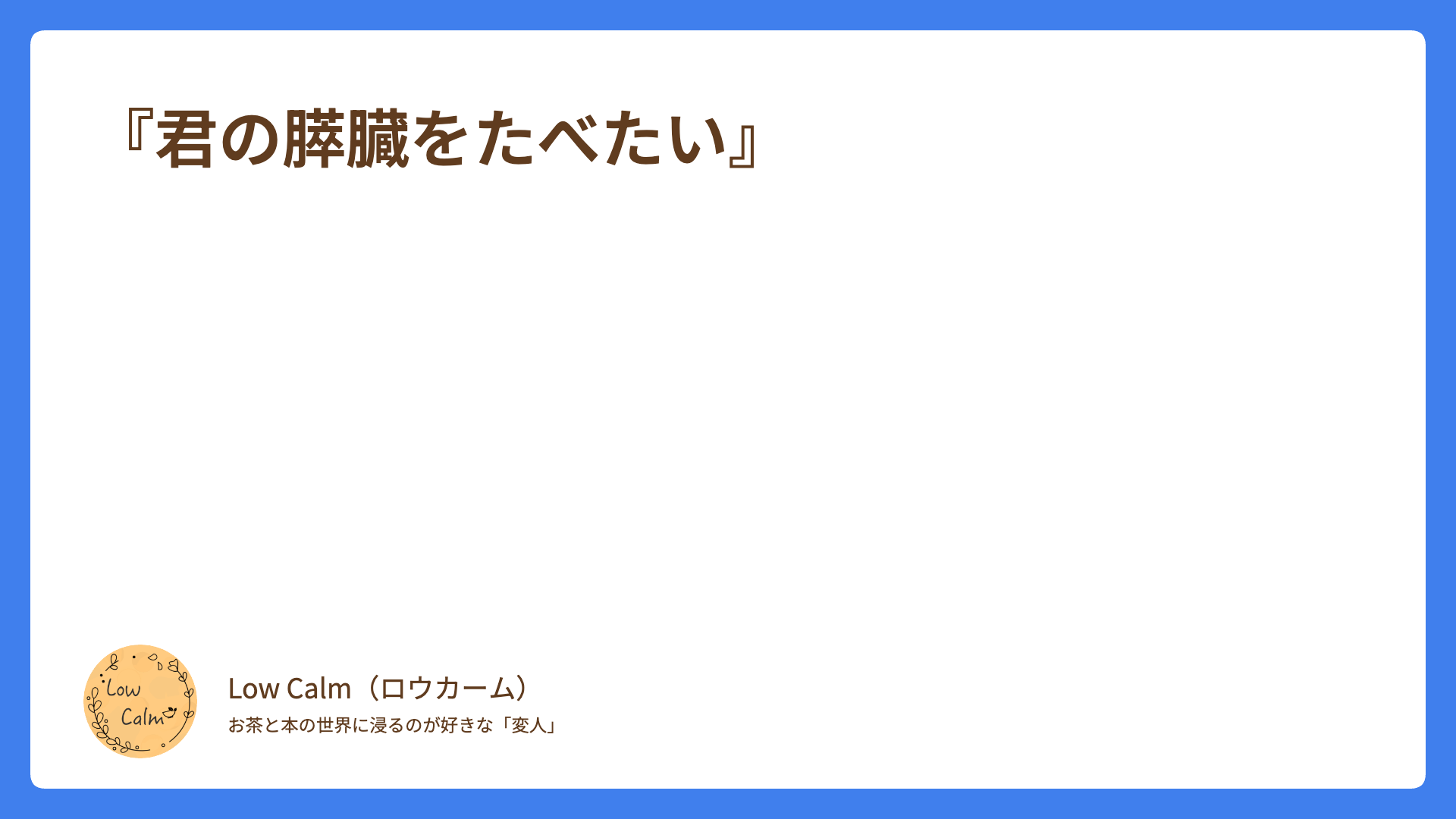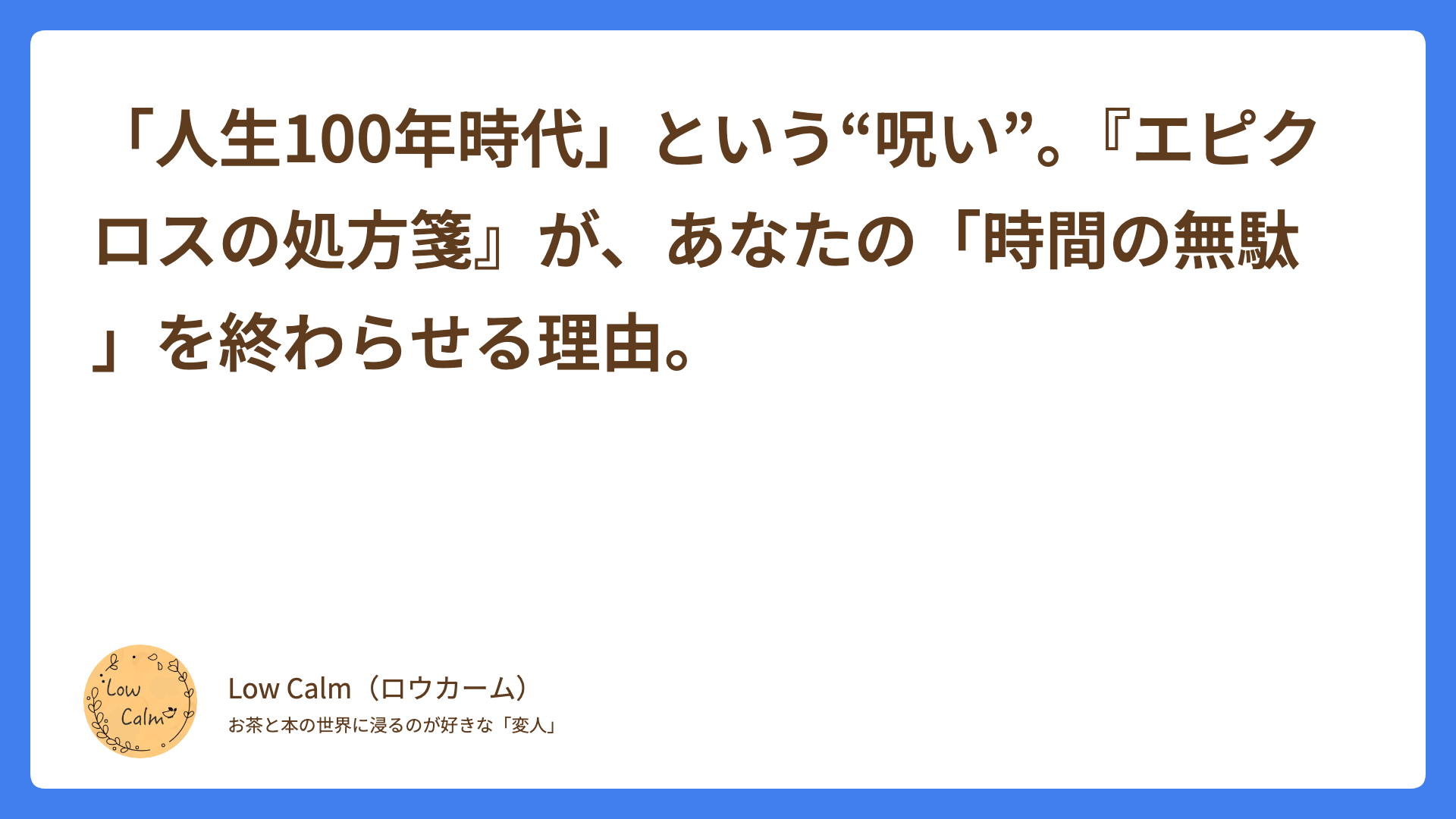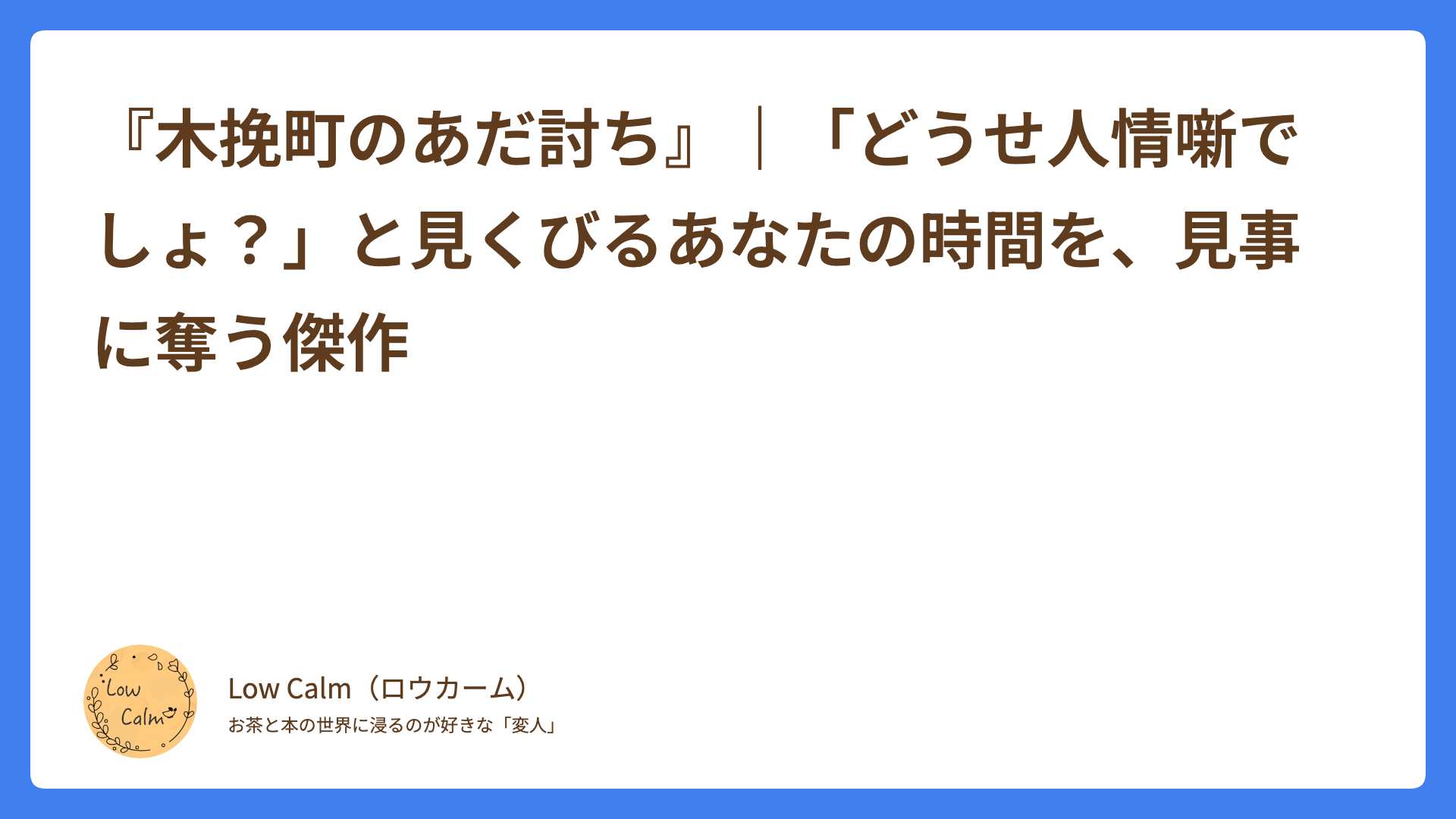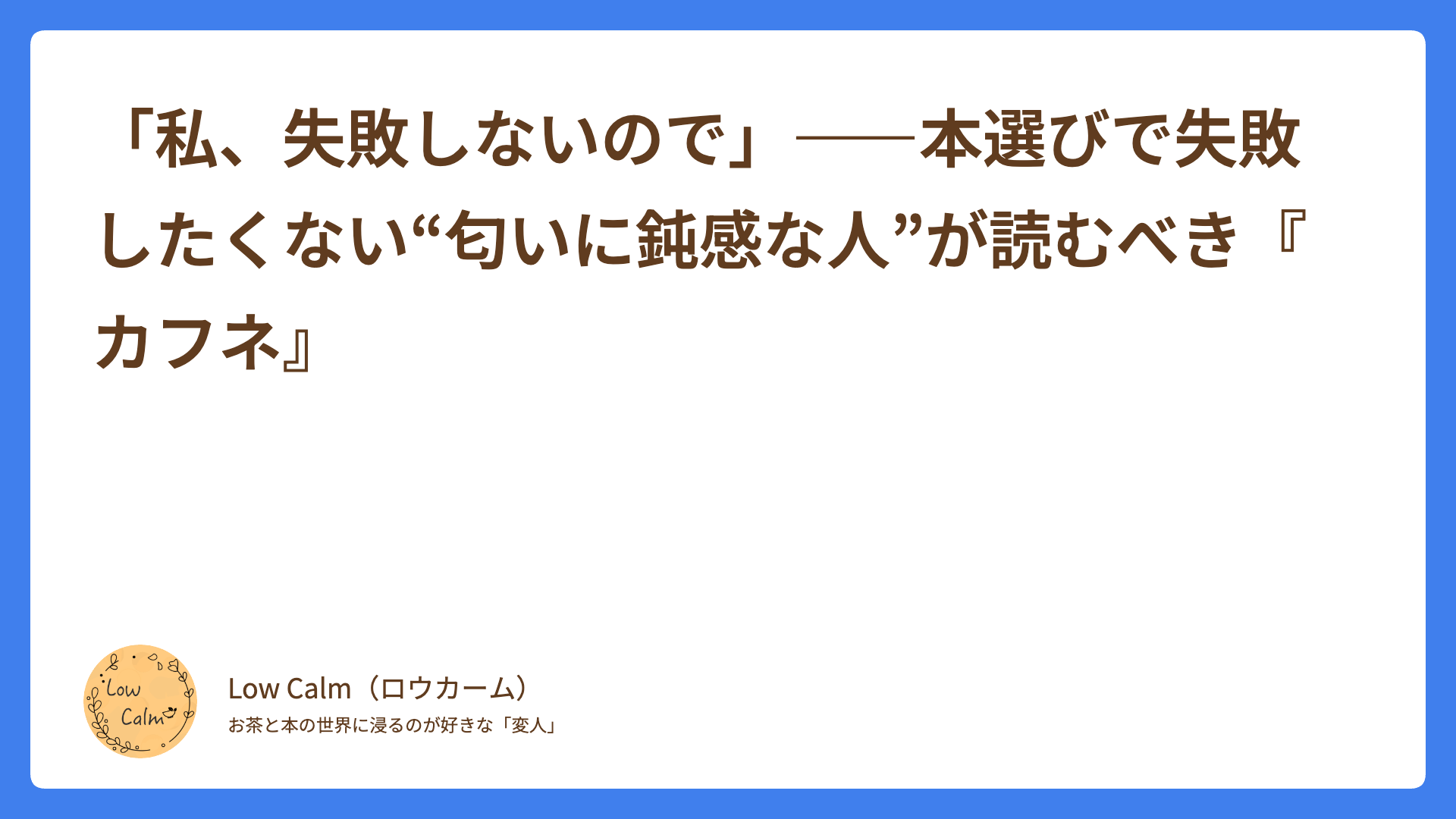『世界で一番透きとおった物語』の感想。仕掛けが凄いが、人を選ぶ理由【ネタバレなし】
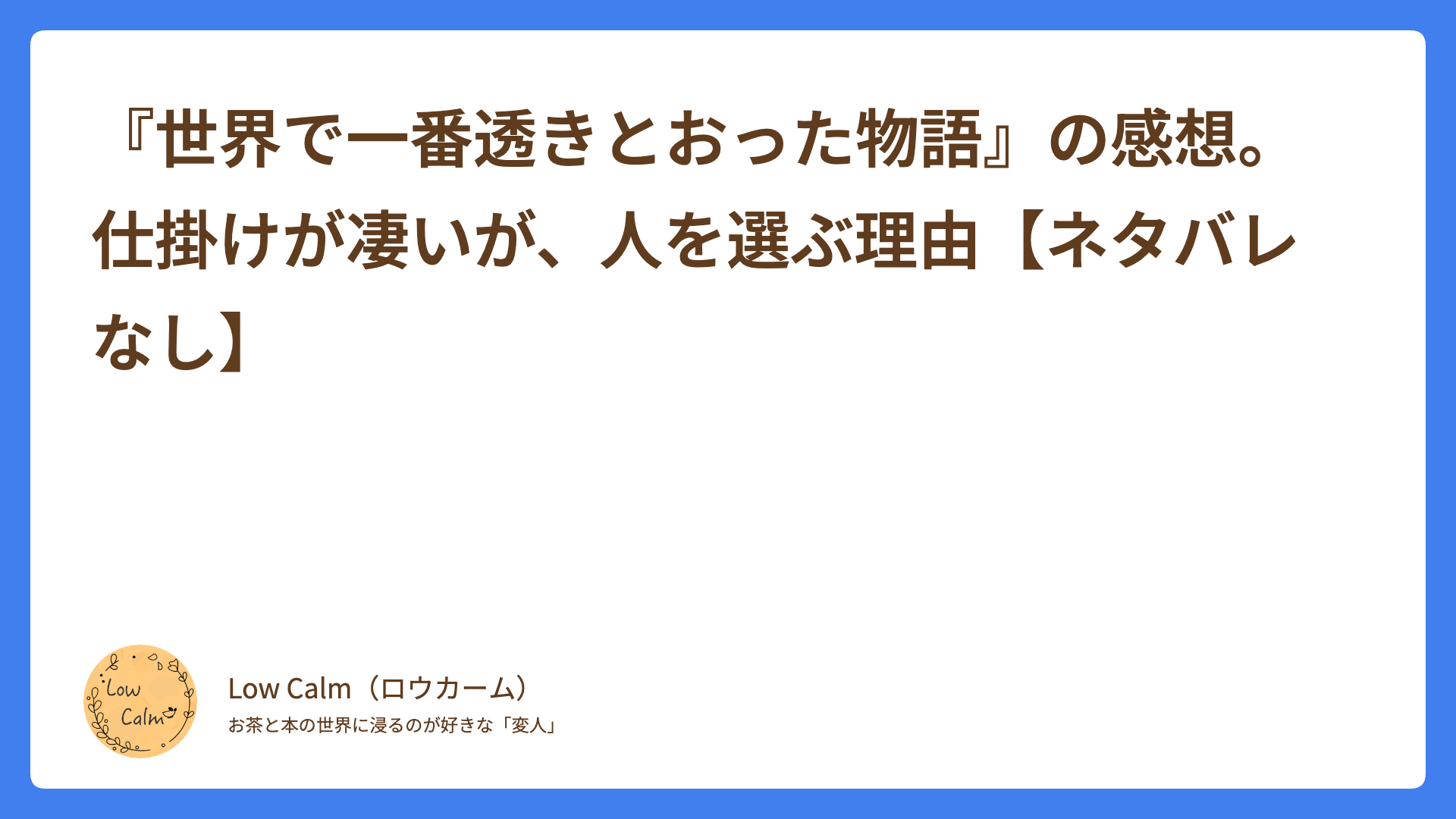
「読書体験が覆る」「絶対に電子書籍で読んではいけない」 発売当初からSNSで賛否両論を巻き起こした一冊、杉井光 著『世界で一番透きとおった物語』。
年間150冊の活字中毒者であり、特に「時間を無駄にさせられた」と感じるミステリを憎む私にとって、これほど挑戦的なキャッチコピーはありません。
- 「本当にすごいの? ただの話題作りじゃない?」
- 「仕掛け(ギミック)はすごくても、物語がつまらないのでは?」
- 「貴重な2時間を、この本に投資する価値はある?」
結論から申し上げます。 「物語」を読みたい人には勧めません。しかし、「読書体験」をしたい人には、これ以上ない「時間の投資」になります。
この記事では、自称「本の変人」である私が、『世界で一番透きとおった物語』がなぜこれほどまでに話題となり、そしてなぜ「人を選ぶ」のかを、ネタバレ一切なしで徹底解剖します。
この記事でわかること
- 本書の「本当にグッときた」独自性
- この本があなたの時間を豊かにするか、奪うか(おすすめな人・ない人)
- SNSでのリアルな口コミ(良いもの・悪いもの)
『世界で一番透きとおった物語』でグッときたところベスト3
私が本書を読み、特に「時間を投資してよかった」と感じた衝撃ポイントを3つに絞り込みました。
1位:物語の「透明性」を、物理的に実現した「本の仕掛け」そのもの
まず、断言します。この本の主役は、登場人物ではなく「本」そのものです。
「透きとおった物語」というタイトル。よくある文学的な比喩だと思って読み進めると、最後の最後で頭を殴られるような衝撃を受けます。「そういうことか!」と。
(引用) ※本書の核心的な仕掛けに関わるため、本文の引用は避けます。
私は職業柄(人事労務)、組織の「透明性(トランスペアレンシー)」という言葉をよく使います。しかし、それはあくまで概念的なもの。
本書は、その「透明性」という概念を、見事に表現しきりました。これは電子書籍では絶対に再現不可能な、紙の本だからこそ成立する「発明」です。
ミステリファンとして様々な「叙述トリック」(文章で読者を騙す手法)に触れてきましたが、本書のトリックは「製本トリック」とでも呼ぶべき、まったく新しいジャンルです。
この「仕掛け」に気づいた瞬間、私は読み終えたばかりの本を、もう一度最初から読み返すことになりました。2時間で読み終え、さらに1時間、その仕掛けの精巧さに感嘆する。これほど濃密な読書体験は、年に一度あるかないかです。
2位:故人が遺した「謎」を追う、切なく儚いミステリプロット
仕掛けばかりが注目されがちですが、もし物語が破綻していれば、私はこの本を閉じていたでしょう。その点、本書は「切ないボーイ・ミーツ・ガール(故人)」の物語として、最低限のラインをしっかりとクリアしています。
物語は、主人公である売れない作家・宮部が、謎の死を遂げた天才作家・藤花(ふみか)の遺稿の「謎」を追う、というものです。
藤花はなぜ死んだのか。彼女が遺した「世界で一番透きとおった物語」とは何だったのか。
私が好む「イヤミス」のような人間の醜悪さはありません。むしろ、その逆。純粋で、触れたら壊れてしまいそうな危うさが全編を支配しています。
この儚い物語の「雰囲気」と、前述した物理的な「仕掛け」が、終盤でピタリと重なります。物語のテーマと本の構造が一体化したとき、読者はタイトルの本当の意味を知るのです。
この構成力は見事としか言えません。
3位:「読者」が「探偵」になる、体験型ミステリであること
本書の「探偵」は、主人公の宮部だけではありません。私たち「読者」自身です。
読み進めていると、ところどころで小さな「違和感」が提示されます。「あれ? この表現、おかしくないか?」「なぜ、わざわざこんな書き方をする?」
その違和感をスルーして読み終えることもできます。 しかし、その違和感を記憶し、仕掛けに気づいたとき、バラバラだったパズルのピースが一気にはまる感覚。
(引用) ※ここも核心に触れるため、具体的な引用は控えます。
「あそこの違和感は、このためだったのか!」
この「アハ体験」こそが、本書の最大のカタルシスです。 本は「読む」だけのものではなく、「体験する」ものであり、「解き明かす」ものである。そんな、本というメディアの可能性を再認識させてくれました。
本を閉じた後、あなたは必ず「誰かにこの体験を話したく」なり、そして「誰にもこの仕掛けをバラしたくない」というジレンマに陥るはずです。
どんな人におすすめなのか
この本は、間違いなく「人を選びます」。あなたの貴重な時間を無駄にしないため、私が「刺さる人」「刺さらない人」を断言します。
📖 この本をおすすめしたい人
- 「新しい読書体験」を求めている人
- 物語を読むだけでなく、本そのもので「驚きたい」「騙されたい」人。
- 物理的な「モノ」としての本が好きな人
- 装丁や紙の手触り、ページをめくる行為自体が好きな「本の変人」(私のような人)。
- 話題の本の「答え」を自分の目で確かめたい人
- 「一体何がそんなにすごいの?」と気になっている人。その答え合わせに、2時間強を投資できる人。
📖 この本をおすすめしない人
- 【最重要】電子書籍(Kindleなど)で読もうとしている人
- 絶対にダメです。100%楽しめません。仕掛けが機能しないため、本当につまらない物語を読まされることになります。お金と時間の無駄です。
- 重厚で複雑な「物語(ストーリー)」を最優先する人
- 物語の展開や人物描写の深さを求める人には、物足りなく感じるでしょう。プロットは比較的シンプルです。
- 伏線回収やロジカルな「謎解き」を期待する本格ミステリファン
- 本書のキモはロジックではなく「ギミック(仕掛け)」です。犯人を当てるタイプのミステリではありません。
目次、著者のプロフィール、本の詳細
目次
序章 第一章 第二章 第三章 第四章 終章
(出典:新潮社 公式サイト)
ご覧の通り、目次は非常にシンプルです。しかし、このシンプルな構成にも、読み終えた後には「なるほど」と思わせる意味が隠されています。
著者のプロフィール
杉井 光(すぎい ひかる)
1978年、東京都生まれ。小説家、ライトノベル作家。 2005年、『火目の巫女』で第12回電撃小説大賞〈銀賞〉を受賞しデビュー。 代表作に「神様のメモ帳」シリーズ、「さよならピアノソナタ」シリーズなどがある。 軽妙な筆致と緻密な構成力、音楽やミステリなど多岐にわたるジャンルを書きこなす筆力に定評がある。
(出典:新潮社 著者プロフィールページを基に、Low calmが要約・再構成)
ライトノベル出身の作家さんですが、その枠に収まらない「仕掛け」への執着と、それを支える確かな筆力を感じる作家です。
本の詳細
- タイトル: 世界で一番透きとおった物語
- 著者: 杉井 光
- 出版社: 新潮文庫nex
- ページ数: 256ページ
- 発売日: 2023年6月28日
まとめ:あなたの時間を「驚き」に変える一冊
あらためて、本書の「グッときたところ」を振り返ります。
- 物理的な「仕掛け」:本というモノの概念を覆す
- 切ない「物語」:故人を追う儚いミステリ
- 読者が「探偵」になる:違和感がカタルシスに変わる体験
これら3つが繋がったとき、「透明な物語」というタイトルが、物理的な仕掛けと物語のテーマの両方を指していることに気づかされます。
本を読んでどう変わったのか(ビフォーアフター)
- 読む前(Before): 「どうせ大したことない。話題先行の、時間を無駄にするタイプの本だろう」 (イヤミス好きとして、斜に構えていました)
- 読んだ後(After): 「参った。これは『物語』ではなく『体験』だ。本というメディアの底力を見せつけられた。この『驚き』のために2時間を費やす価値は、間違いなくあった」
私自身、本は「情報や物語を得るためのツール」として捉えがちでした。しかし本書を読んで、「本はそれ自体が作品(アート)であり、触覚や視覚を含めた五感で『体験』するものだ」と、本好きとしての原点を思い出させられました。
あなたが取るべき具体的なアクションプラン
もし、あなたがこの本に少しでも興味を持ったなら、取るべき行動は一つだけです。
アクションプラン: 今すぐ、Kindleや楽天koboのカートからこの本を削除し、書店に向かうか、紙の書籍を注文してください。
そして、誰にも邪魔されない静かな時間(できれば美味しいお茶と共に)を2時間確保し、その「体験」に没入してください。
あなたの読書史に、忘れられない「驚き」が刻まれることを、私(Low calm)が保証します。