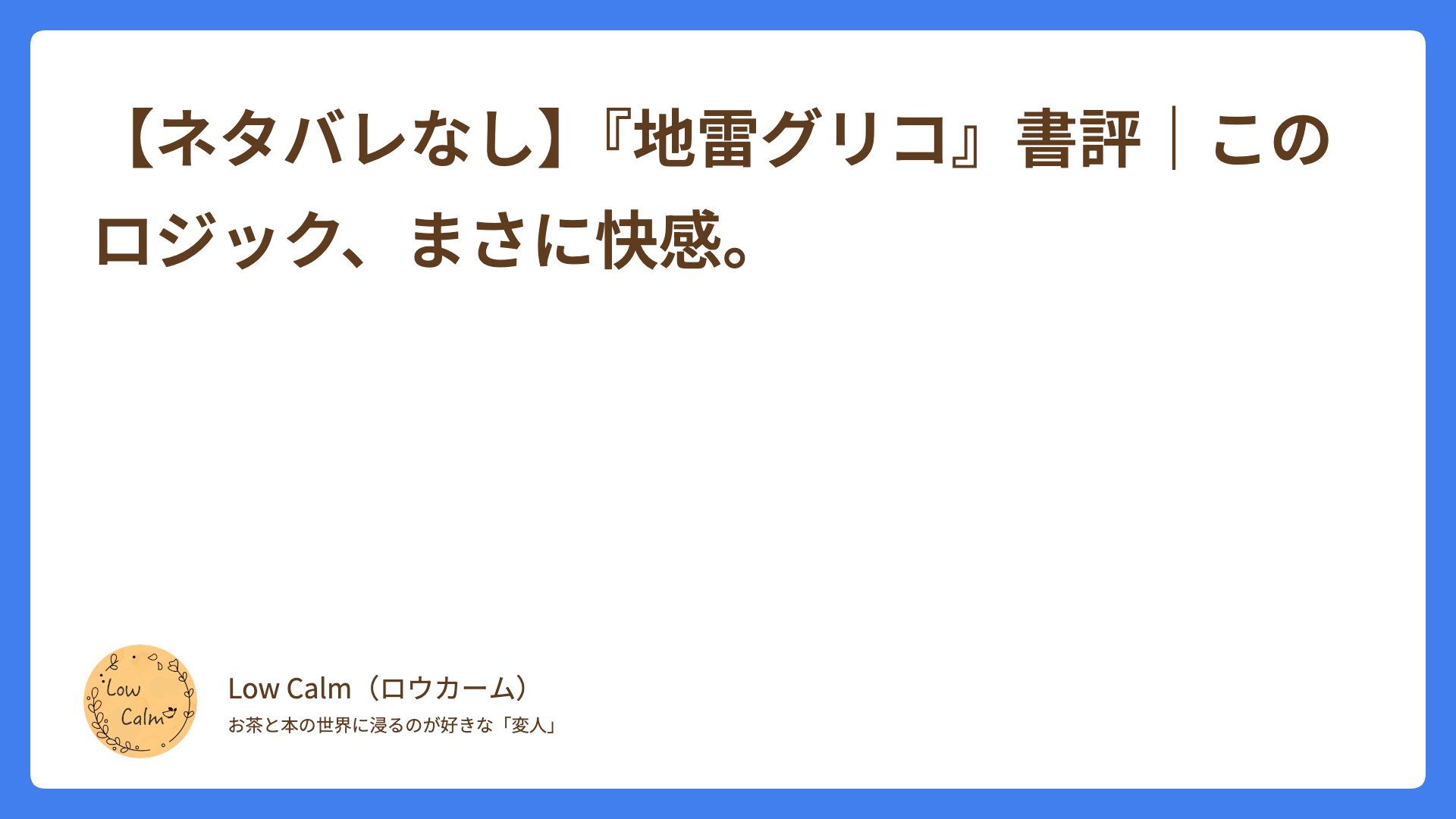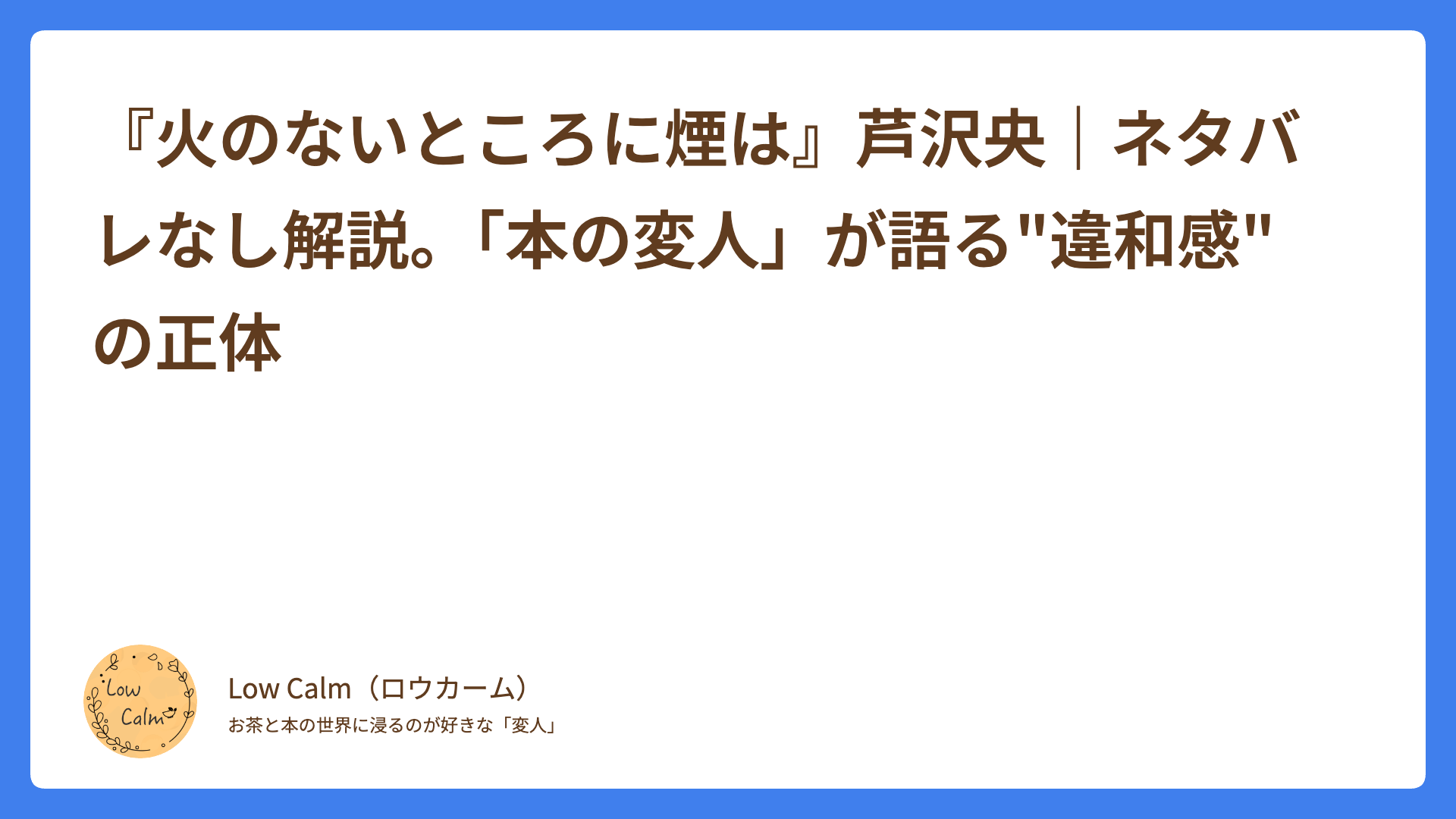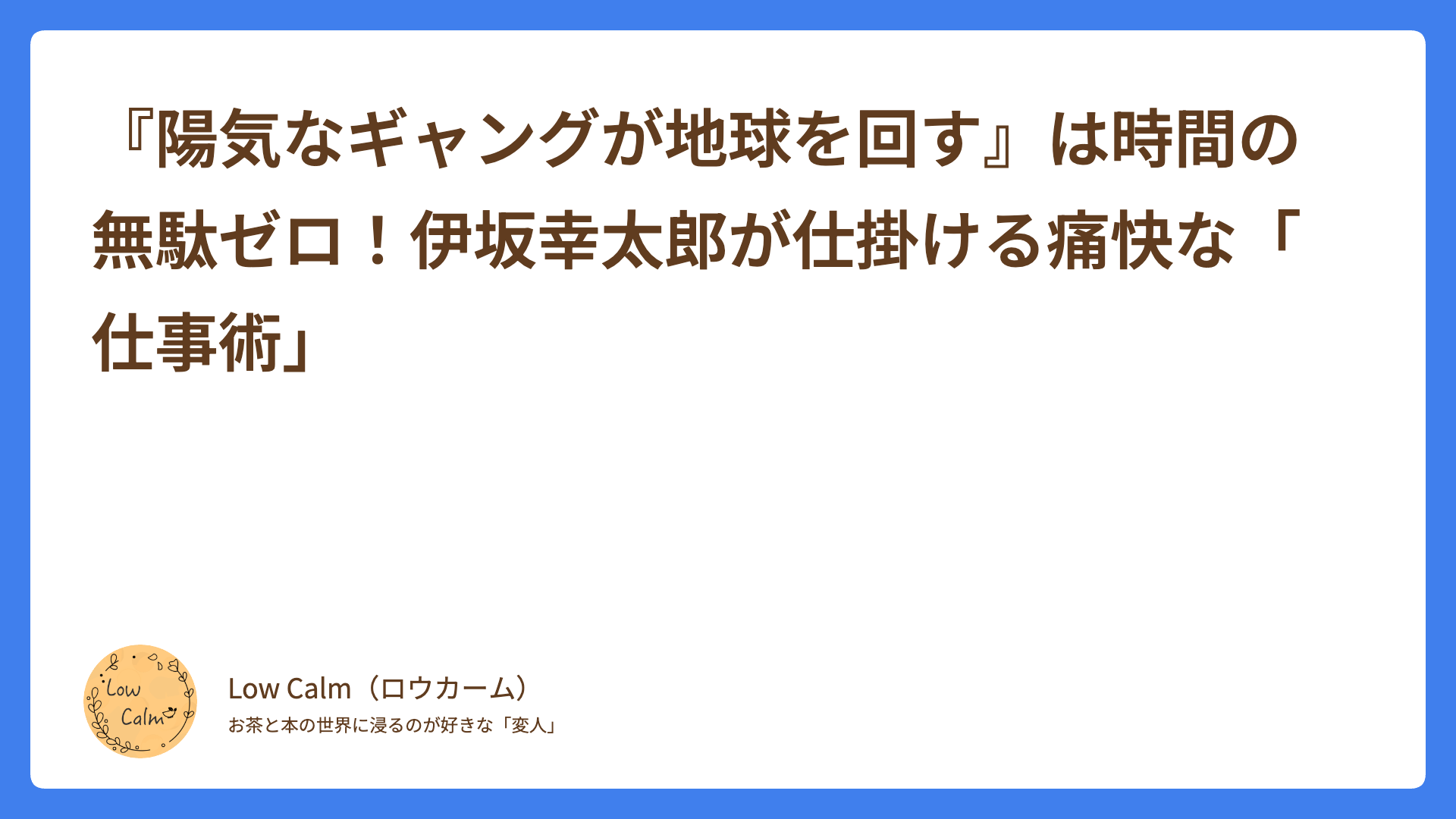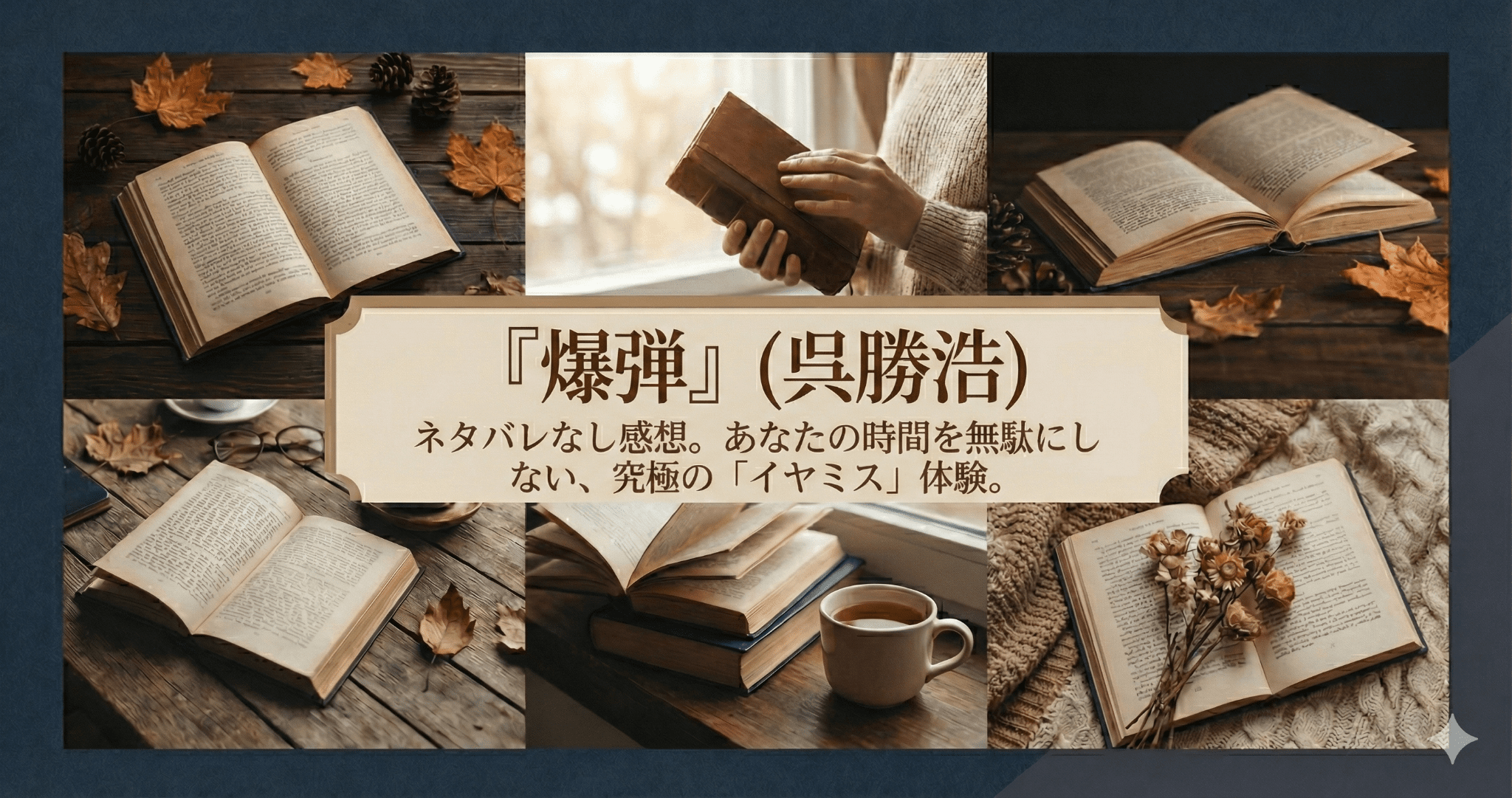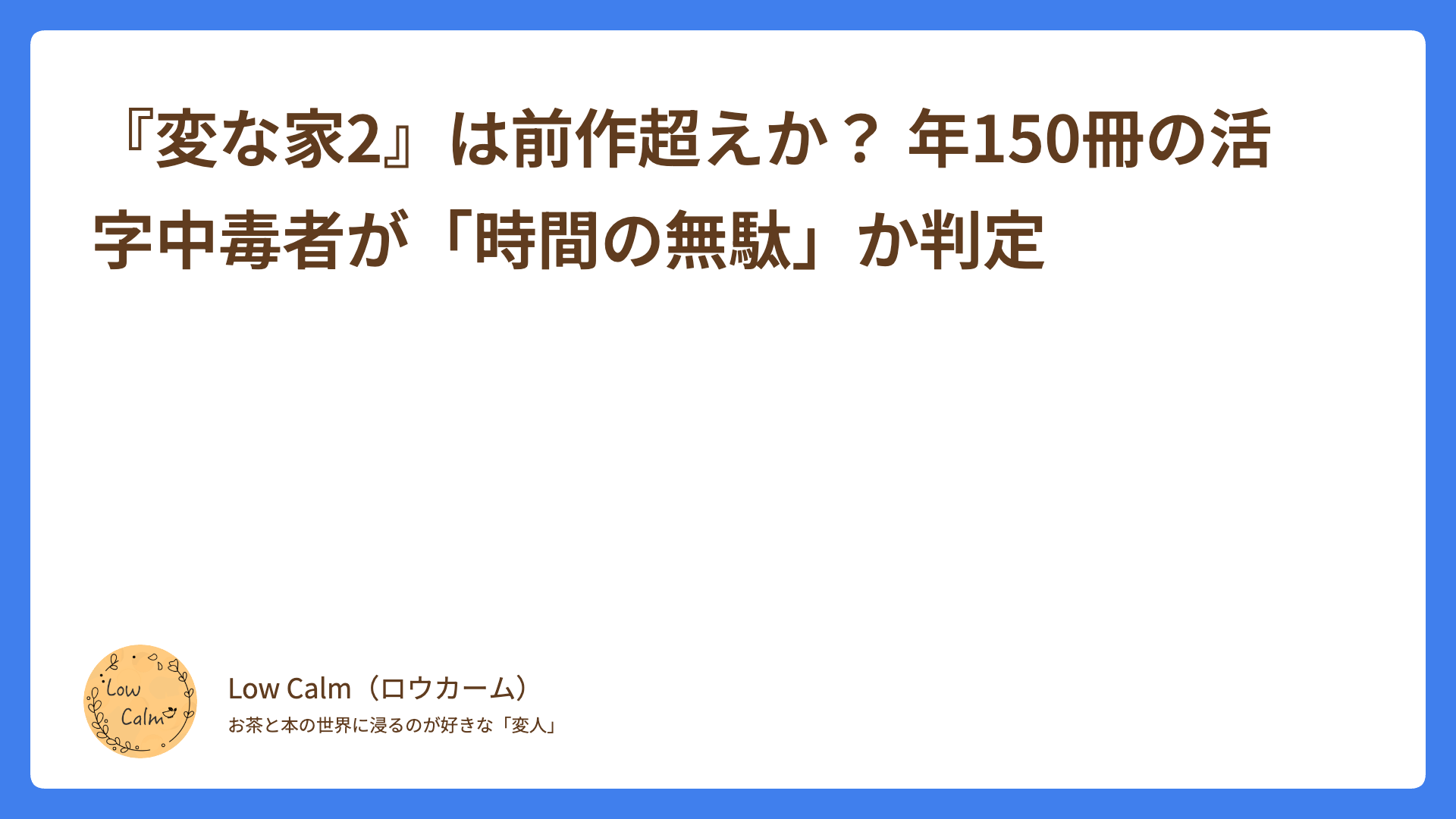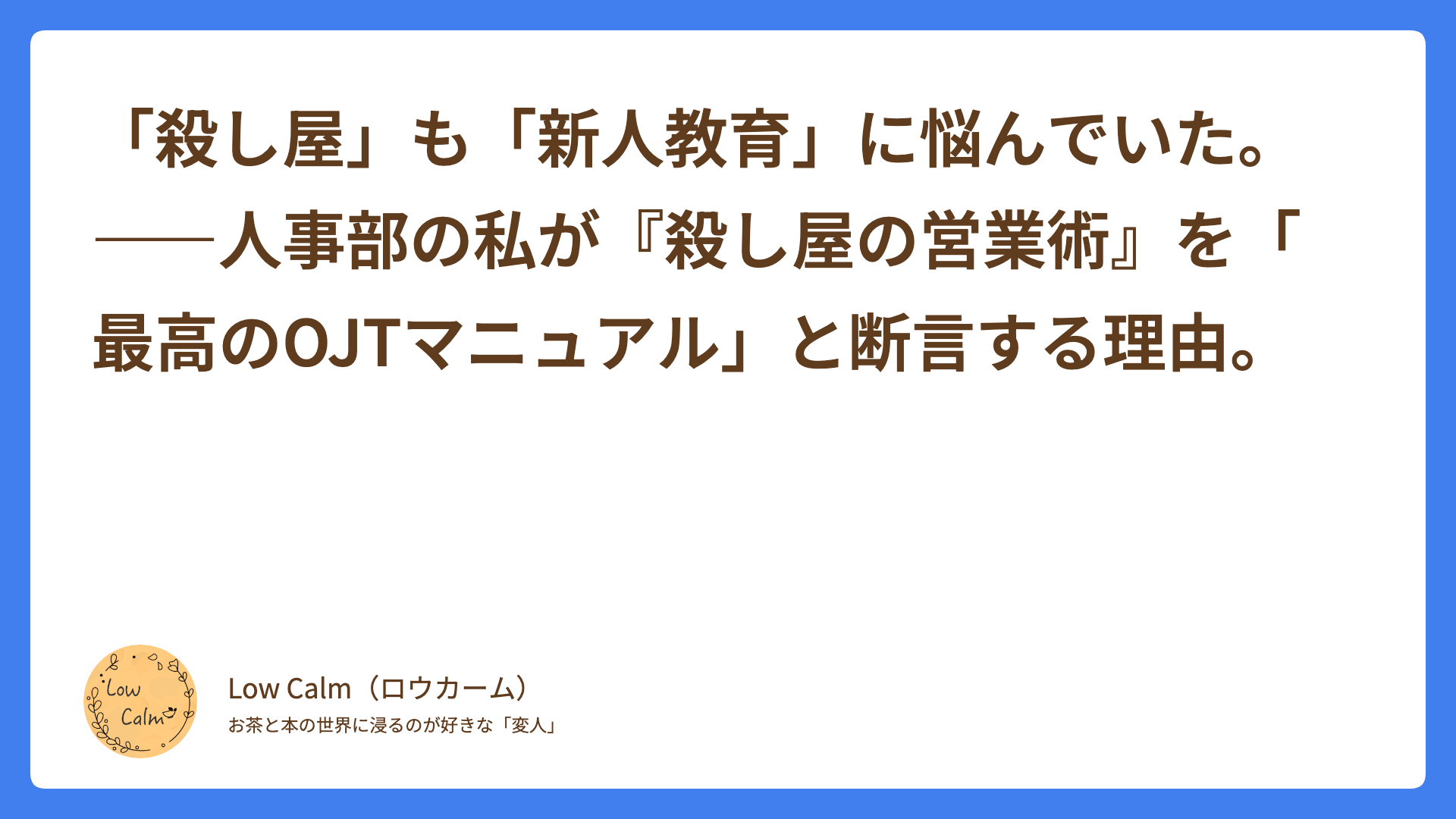『変な家』(雨穴) – 間取り図に隠された恐怖の正体とは【ネタバレなし】
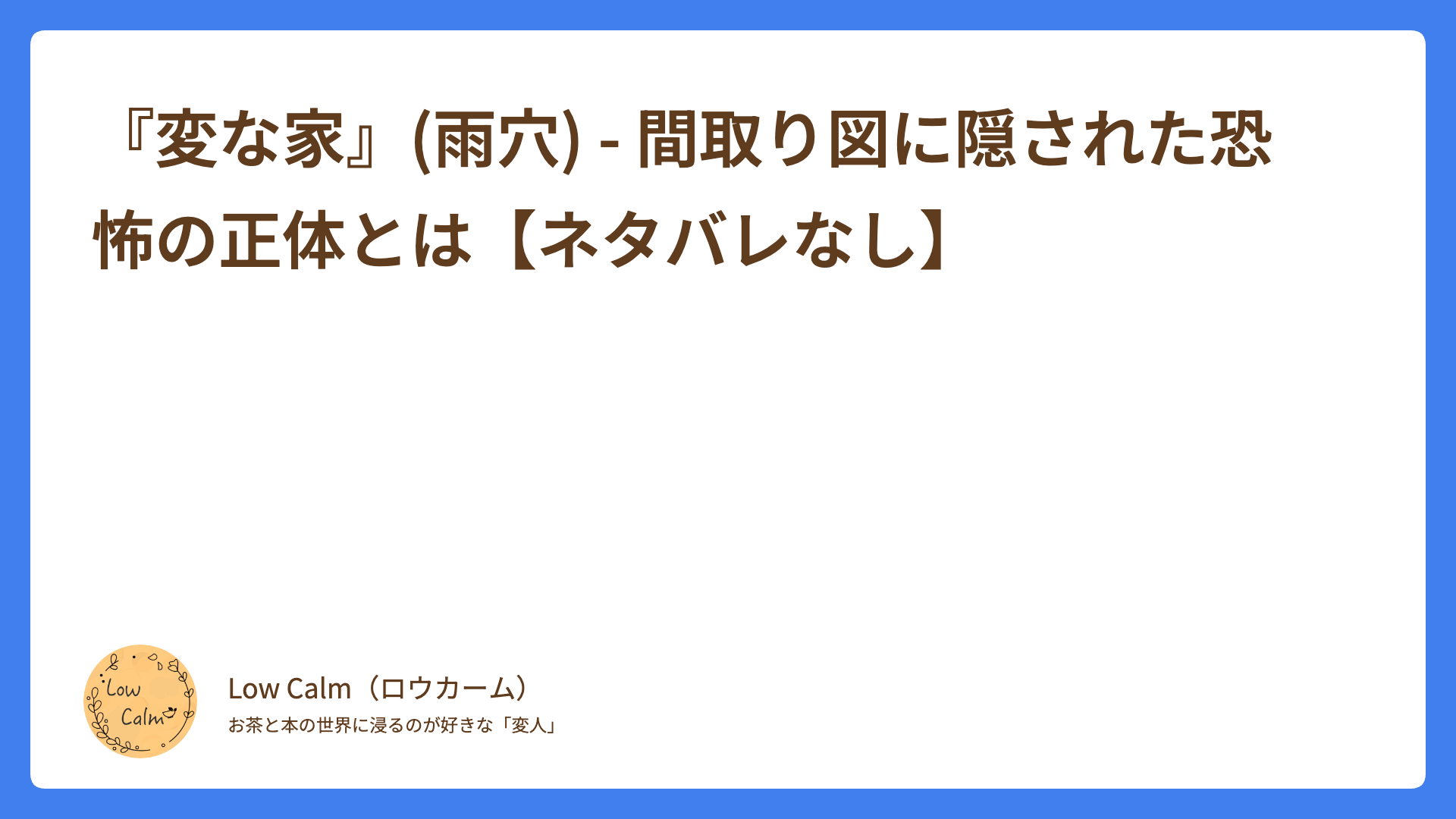
あなたは、間取り図を見ただけで「何かおかしい」と感じたことはありますか?
もし、その違和感の先に、想像を絶するような人間の闇が隠されていたとしたら……。
今回ご紹介するのは、発売直後から「恐ろしすぎて最後まで読めない」「この謎が解けたら天才」とSNSやYouTubeを席巻した、雨穴(うけつ)氏による大ヒット作『変な家』です。
映画化もされ、その勢いはとどまるところを知りませんが、原作小説は「活字で読むからこその恐怖」が凝縮されています。
この記事では、年間150冊の活字中毒者であり、特にミステリを愛する私、Low calmが、「なぜこの本がこれほどまでに人々を惹きつけるのか」を、ネタバレ一切なしで徹底的に解剖します。
この記事でわかること
- 『変な家』が「ただのホラー」ではない理由
- 私が本気で震えた「グッときた」ポイント ベスト3
- あなたが『変な家』を読むべきか、読まないべきか
本記事の信頼性
私、Low calmは、普段は会社員として人事労務管理というロジカルな仕事をしていますが、その実態は年間約150冊を読破する活字中毒者です。特に「イヤミス(読んだ後に嫌な気分になるミステリ)」と純文学をこよなく愛しています。
当ブログのモットーは「あなたの時間を大切にすること」。本選びで絶対に失敗したくない私が、忖度なしで「読む価値があるか」を正直にお伝えします。
なぜ、今『変な家』なのか
「流行っている本は、中身が薄いんじゃないか?」 「ホラーは苦手だから、自分には関係ないかも…」
そう思っている方こそ、この記事を読み進めてください。本書は、単なる幽霊屋敷の話ではありません。一見するとごく普通の間取り図に潜む「人間の意図」を、論理的に、そして冷徹に解き明かしていく不動産ミステリーなのです。
この記事を読み終える頃には、あなたが普段何気なく見ている「間取り図」が、全く別のものに見えてくるかもしれません。
それでは、この奇妙な家の扉を、一緒に開けてみましょう。
📖 私が慄然とした『変な家』のグッときたところベスト3
本書は、読書感想文のお手本(『だれでも書ける最高の読書感想文』)にもあるように、「グッときたところ」=「心を揺さぶられた箇所」の宝庫です。
私が特に「これはただ事ではない」と感じ、背筋が凍ったポイントを3つ厳選しました。
第1位:違和感の正体。「窓のない子供部屋」の真の役割
物語は、主人公である「私」が、知人の栗原さん(オカルト専門の設計士)に、ある「変な家」の間取り図を見せるところから始まります。
「この家、何かがおかしいんです」
一見、どこにでもあるような一戸建て。しかし、よく見るとそこには「謎の空間」が存在します。そして、最も不可解なのが「一階と二階にある、窓のない子供部屋」です。
栗原さんは、この二つの部屋が奇妙な形で繋がっていることを指摘し、ある「仮説」を立てます。
私が最も衝撃を受けたのは、この「仮説」が提示された瞬間です。
なぜ、グッときたのか。
それは、この「窓のない子供部屋」の存在理由が、単なる設計ミスや、我々が想像するような「子供を閉じ込めるため」といった単純な悪意ではなかったからです。
そこには、もっと合理的で、冷徹で、そして何かの目的のために最適化された「意図」が存在しました。
ミステリ好きとして、「なぜそうなっているのか?」というロジICを追い求めるのが好きな私にとって、この「窓のない部屋」の謎が解き明かされた時、その異常なほどの合理性に、恐怖よりも先に「なるほど、そう使うのか」という歪んだ感心すら覚えてしまいました。
これは、人間の倫理観が欠如した場所で、ただ「目的」のためだけに設計された「機能」なのです。その機能が何なのかは、ぜひ本書で確かめてください。ただのホラーではない、設計ミステリーとしての秀逸さに震えました。
第2位:連鎖する間取り図。点と点が線になる瞬間の悪寒
この物語は、一つの「変な家」だけで終わりません。
最初の謎が、さらなる謎を呼びます。主人公たちは、この家の過去を調査するうちに、全く別の場所、別の時代に建てられた「いびつな間取り図」に次々と遭遇するのです。
一見、何の関係もないように思える複数の間取り図。しかし、栗原さんがそれらを比較・分析していくうちに、恐ろしい「共通点」が浮かび上がってきます。
なぜ、グッときたのか。
それは、「バラバラだったパズルのピースが、一つの悍(おぞ)ましい絵を完成させる瞬間」を見事に描き切っているからです。
最初は小さな「違和感」だったものが、調査が進むにつれ、ある特定の「儀式」や「因習」の存在を浮かび上がらせていきます。
私は普段、人事労務の仕事で、バラバラの事象から規則性を見つけ、就業規則などのルールを作ることがあります。だからこそ、この「共通点を探し出し、法則性(この場合は悪しき伝統)を見抜く」という栗原さんの推理プロセスに、強烈に引き込まれました。
読者である私たちも、主人公たちと一緒に間取り図を睨みながら、「まさか、あの空間は、この家でも…?」と推理に参加させられます。そして、その推理が的中した時、喜びではなく恐怖が襲ってくる。この構成力は見事というほかありません。
第3位:会話文主体で進む、圧倒的な「読みやすさ」と「スピード感」
本書は、その内容の恐ろしさとは裏腹に、驚くほど読みやすい構成になっています。
その最大の理由は、物語の大部分が、主人公の「私」と設計士の「栗原さん」との会話形式で進む点にあります。
私:「この空間は、一体何なんでしょう?」 栗原:「おそらく、これは〇〇のために使われたんですよ」
このようなテンポの良い対話によって、読者はまるで二人の会話を隣で聞いているかのような、あるいはYouTubeの動画を見ているかのような感覚で、複雑な謎解きに没入できます。
なぜ、グッときたのか。
正直に告白します。私は純文学も愛好するため、普段から重厚で緻密な描写の小説を読み慣れています。そのため、当初は「会話文ばかりの本は、物足りないのではないか」と少し侮っていました。
しかし、それは大きな間違いでした。
『変な家』において、この「会話形式」は、恐怖を増幅させる最強の装置として機能しています。
難しい心理描写や情景描写をあえて削ぎ落とし、間取り図という「事実」と、そこから導き出される「仮説」だけで物語を推進させる。これにより、読者は息つく暇もなく、次々と提示される恐怖の事実に直面させられます。
読みやすいからこそ、ページをめくる手が止まらない。止まらないからこそ、恐怖の核心へと一気に連れて行かれる。このスピード感は、まさに「活字中毒者」の私にとっても、新鮮な読書体験でした。
👤『変な家』はどんな人におすすめなのか
この本は、間違いなく「人を選ぶ」作品です。私の独断と偏見で、「読むべき人」と「読まない方がいい人」をハッキリと分類します。
おすすめな人
- 「間取り図」を見るのが好きな人 これは絶対です。不動産サイトや新築のチラシを見て「この動線は…」「この収納は…」と考えるのが好きな人は、間違いなく本書の「違和感」に気づき、ゾクゾクできるはずです。あなたの「間取り図リテラシー」が試されます。
- ホラーは苦手だが、論理的な「謎解き」が好きな人 本書は幽霊がドーンと出てくるようなオカルトホラーというより、「なぜ、こんな設計にしたのか?」という論理の積み重ねで恐怖を構築するミステリーです。怖いけれど、謎が解ける瞬間のカタルシス(?)を味わいたい知的な方におすすめです。
- 普段あまり本を読まないが、映画やYouTubeは好きな人 前述の通り、会話文主体で非常にテンポが良く、動画的なエンターテイメント性が高い作品です。読書が苦手な人でも、スナック感覚で一気に読み終えてしまうでしょう。「活字の面白さ」を知る入り口として、これ以上ない一冊です。
おすすめしない人
- 「人間の底知れない悪意」や「因習」に強い嫌悪感を抱く人 本書で描かれる恐怖の根源は、超常現象ではなく、「人間」そのものです。特に、閉鎖的なコミュニティで受け継がれる「常軌を逸したしきたり」が核となっています。読んだ後、確実に重く、嫌な気分になります。(私のようなイヤミス好きにはご馳走ですが…)
- 緻密な人物描写や、美しい文章表現を小説に求める人 スピード感を重視するあまり、登場人物の「内面」や「葛藤」といった心理描写は意図的に省かれています。純文学のような「行間を読む」楽しみや、文学的な余韻を求める方には、物足りなく感じるでしょう。
- 「間取り図」に一切の興味が持てない人 物語のすべてが「間取り図」から始まります。この図面を見て「ふーん」としか思えない場合、恐怖の核心に迫る「違和感」を共有することが難しく、面白さが半減してしまう可能性が高いです。
📚 目次、著者のプロフィール、本の詳細
本書の構造を理解するために、公式な情報を確認しておきましょう。
目次
第一章 変な家
第二章 いびつな間取り図
第三章 記憶の中の間取り
第四章 縛られた家
出典元: 株式会社 飛鳥新社 参照URL:
https://www.asukashinsha.co.jp/bookinfo/9784864108454.php
この目次からも、物語が「一つの家」から始まり、次第に「複数の間取り図」、そして「過去の記憶」へとスケールアップしていく様子が伺えます。
著者のプロフィール
雨穴(うけつ)
日本のウェブライター、小説家、YouTuber。 本名、素顔、地声などは一切非公開の覆面作家として知られています。白い仮面と黒い衣装がトレードマーク。
インターネットメディア「オモコロ」のライターとしても活動しており、独特の世界観を持つ記事や動画で人気を博しています。
本書『変な家』は、もともとYouTubeに投稿された動画が原型となっており、それが爆発的な人気を呼び、小説家としてデビューするきっかけとなりました。まさに、現代のインターネットが生んだスター作家と言えます。
本の詳細
- ISBN: 978-4-86410-845-4
- 書名: 変な家
- 著者: 雨穴
- 出版社: 飛鳥新社
- 発売日: 2021年7月20日
- ページ数: 248ページ
🏁 まとめ:「変な家」は、あなたの日常に潜む「違和感」を炙り出す一冊
さて、この奇妙な家のツアーも終わりです。
改めて、私が選んだ「グッときたところベスト3」を振り返ってみましょう。
- 「窓のない子供部屋」が持つ、冷徹なほどの合理性
- 点と点(複数の間取り図)が繋がり、悍ましい線(因習)となる構成力
- 会話文主体が生み出す、恐怖のジェットコースターのようなスピード感
これら3つの要素を繋ぎ合わせると、見えてくるものがあります。
それは、『変な家』が、私たちの「日常」と「異常」の境界線を曖昧にする作品であるということです。
本書を読む前、私にとって「間取り図」は、単なる「家の設計図」であり、効率的な生活を営むための合理性の象徴でした。
しかし、本書を読んだ後、私にとって「間取り図」は、**「そこに住む人間の意図(あるいは悪意)が凝縮されたテキスト」**へと変貌しました。
私たちは普段、日常に潜む小さな「違和感」を見過ごしがちです。 「この部屋、なんだか使いづらいな」 「なぜ、こんな場所に扉があるんだろう?」 その違和感を、「まあ、そういう設計なんだろう」と無理やり納得させていませんか?
『変な家』は、その「違和感」にこそ真実が隠されていると教えてくれます。
もし、あなたが今、自分の住んでいる家の間取り図を見て、少しでも「おかしい」と感じる部分があるのなら……。
具体的なアクションプランとして、本書の主人公たちのように、「なぜ、そうなっているのか?」と深く考えてみてください。
その「なぜ」の先に、この『変な家』のような深い闇が隠されているとは限りません。しかし、設計者の意図や、かつての住人の暮らしぶりを想像する「知的なゲーム」として、あなたの日常は少しだけスリリングなものになるはずです。
この本は、あなたの「見る目」を変えてしまう一冊です。 本選びで失敗したくないあなたに、私はこの「最悪の読後感(最高の賛辞です)」を、自信を持ってお勧めします。